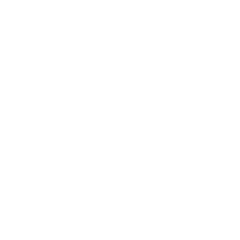News
2017/1~
2018年2月24日(土)日刊木材新聞より
GIR研究会が発足 SMB建材等6社で
訴求力高め市場活性化目指す
SMB建材(東京都、角柄明彦社長)木構造建築部(小川嘉男部長)を発起人に、グルード・イン・ロッド(鋼棒挿入接着接合、GIR)技術を持つ企業で構成されるGIR研究会が22日に発足した。同研究会は、GIR技術に関する意見交換や開発、木構造市場の動向や法令改正などの情報共有を図り、GIR技術の向上やGIRの市場開拓につなげていくことが狙い。昨年度から設立に向けた話し合いを重ね、22日から本格的な活動を開始することで合意した。
会員企業は、翠豊(岐阜県加茂郡、今井潔志社長)、スクリムテックジャパン(福岡県筑紫野市、河野泰之社長)、中東(石川県能美市、小坂勇治社長)、藤寿産業(福島県郡山市、蔭山寿一社長)、山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)、SMB建材木構造建築部の6社。
会長には小川SMB建材木構造建築部部長が就く。産官学連携を視野に、腰原幹雄東京大学生産技術研究所教授を顧問に迎えた。
GIRは、木質部材に開けた穴に鋼棒を挿入し、樹脂接着剤を充填することで部材同士を接合する方法。国内では、サミットHR工法やホームコネクター工法、RH構法などが展開されている。中大規模木造の構造躯体で用いられるだけでなく、戸建て住宅にまで幅広く利用されているほか、仕上げ内外装材にも活用されている。
一方で、企業がそれぞれに独自工法として展開しているのが現状で、GIRが汎用性のある工法になっていないという課題があった。
こうした課題を背景に、同研究会では、同会を通じて緩やかな企業連携を形成することで、GIRの啓蒙や普及、技術の共有を図ることなどでGIRの訴求力を高めていく。
当面、同研究会が対象とするGIRは、サミットHR工法、ホームコネクター工法、RH構法の3つとする。だが将来的には、他のGIR技術を基にする各社との連携も視野に入れていく。
同研究会では今後、広報学科会や技術分科会を設け、GIRのさらなる認知度の向上と、CLTへのGIRの適用、GIRの耐火構造への応用、靱性を持ったGIRの開発や施工性といった技術面の課題などに取り組んでいく。
さらに、標準接合基準の整備と共有を通じ、会員企業がそれぞれにGIR技術を一層磨いていく。
2018年2月16日(金)
CLT関連 林野庁委託事業成果報告会が開催されます
平成28・29年度のCLT関連林野庁委託事業17件について事業報告が行われます。当社も2件報告いたします。
・日 時:平成30年3月5日(月) 10:00~16:00
・会 場:全国町村議員会館 2階大会議室 (東京都千代田区一番町25)
・定 員:先着160名 要申込 入場無料 ※定員に達し次第、申込受付終了
・申込み:日本CLT協会のホームページよりお願いします。
2018年2月9日(金)
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター主催
CLTを活用した建築物等実証事業成果報告会
「CLTがもたらす新たな建築の世界」が開催されます
CLT実証事業を活用した21物件について、東京会場で10件、大阪会場で11件の事業報告が行われます。
■東京会場(成果報告会、住木センター講演会合同開催)
・日 時:平成30年3月8日(木) 11:00~16:30
・会 場:すまい・るホール (東京都文京区後楽1-4-10)
・定 員:先着300名 要申込 入場無料 ※定員に達し次第、申込受付終了
・申込み:住木センターホームページよりお願いします。

■大阪会場(成果報告会)
・日 時:平成30年3月12日(月) 13:00~17:20
・会 場:グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)会議室1202(大阪府大阪市北区中之島5-3-51)
・定 員:先着200名 要申込 入場無料
・申込み:住木センターホームページよりお願いします。

鹿児島県主催
木造建築関連技術者向けCLT技術講習会が開催されます
鹿児島県主催でCLTについての技術講習会が開催され、当社が講師をつとめます。
2017年2月に開催したものと基本的には同じ内容です。
・日時:2018年2月9日(金)10:30~15:40
・場所:鹿児島県社会福祉センター 7階大会議室(定員50名)
(鹿児島市鴨池新町1-7 TEL:099-251-3232)
※駐車場が満車の場合は鹿児島県庁駐車場をご利用ください
・参加費:無料
・内容:1.CLTの特徴と性能
2.CLTを活用した建築事例
3.国土交通省告示の解説
4.CLTを活用した建築設計手法 ※詳細は添付PDFをご参照ください
・申込:添付PDF裏面の申込用紙に必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・締切:2018年2月2日(金)※定員になり次第終了
・お問い合わせ先:鹿児島県木造住宅推進協議会事務局
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター企画部企画課
TEL 099-224-4543/FAX 099-226-3963
2018年1月11日(木)
Aパネ工法(木造在来軸組+CLT) 説明会が開催されます
当社が製造している厚さ36mmのCLT(Aパネ)を木造在来軸組の構造用面材として利用した「Aパネ工法」の説明会が東京で開催されます。施工事例紹介や設計・施工方法の解説などです。
・日時:2018年2月22日(木)13:30~16:30
・場所:一般社団法人 日本CLT協会(定員20名)
(東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋2F)
・参加費:無料
・申込:添付PDFに必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・締切:2018年2月15日(木)※定員になり次第終了
・お問い合わせ先:Aパネ工法普及協議会事務局
https://www.apane-clt.com/ TEL 058-370-1884/FAX 058-271-5630
2018年1月15日(月)
近畿木材利用建築促進フォーラム~CLT等様々な木材の利活用~が開催されます
林野庁・近畿中国森林管理局と国土交通省・近畿地方整備局が共に開催する初の取り組み。
山側から建築まで一体として情報提供されます。
・日時:2018年2月15日(木)14:00~17:30
・場所:近畿中国森林管理局 4階大会議室
(大阪市北区天満橋1丁目8番75号)
・参加費:無料
・申込:添付PDFに必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・プレスリリース:
林野庁 近畿中国森林管理局
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/press/hanbai/180105.html
国土交通省 近畿地方整備局
http://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2017/20180105-2.html
2017年12月16日(土)日刊木材新聞より
CLT設計・構造見学会
新潟県
新潟県はこのほど、胎内市でCLT工法による県立青少年教育施設(仮称)野外活動支援棟の設計実例・構造見学講習会を開いた。県内では今年度、これを含め5カ所でCLT建築が進められており、越後杉の活用を図っている。
この建物は木造CLT工法2階建て、延べ床面積約355平方㍍。1階と2階の壁、床にCLTを使用しており、1階壁床3211×1500×210㍉、2階壁2990×1500×210㍉、2階とRF床3999×1874×150㍉など。CLT製造は山佐木材、加工は志田材木店、意匠設計が石動建築設計事務所、構造設計が建構造研究所、施工が小野組。
当日は意匠、構造、施工の各担当者がCLT工法、建物について説明した。計画上の留意点については、準耐火構造が可能(燃えしろが必要)であること、仕上げの有無で対応の違いがあること(同施設はCLTのアピールから現し・金物をいかに目立たなくするか)などについて説明した。
このほかCLTの強度等級の種類、配置条件、金物の種類、耐力、開口部を設けた場合の断面性能低減、加工精度の確保、建て方などについて解説した。
同県は、今年度から越後のふるさと木づかい事業を拡充し、非住宅分野や中層での県産材利用を推進するため、木造・木質化の新技術を採用した先導性・モデル性の高い施設(商業施設を含む)に対して補助を行っており、その制度についても説明した。
2017年12月7日(木)日刊木材新聞より
木造3階建ての福祉施設建設中
床などにCLT、遮音性能など検証へ 南東北春日デイサービスセンター
木造3階建ての老人デイサービス兼事務所が福島県須賀川市で建設中だ。「南東北春日デイサービスセンター(仮称)」は集成材ラーメン構造で建設されており、壁や階段、2階と3階部分の床にはCLTが使われている。完成は来年1月末を予定している。
この建物の敷地面積は約500平方㍍で、延べ床面積1309.45平方㍍、最高高さ9922㍉。老人デイサービスセンターは本来であれば耐火構造物となるが、3階を事務所として使うため、準耐火建築物として設計している。そのため、構造躯体の一部を現しとして使うことができる。
柱や梁など集成材を使う部分には県産カラ松、一般材部分には県産杉を使用するなど、福島県産材が随所に生かされている。CLTは国産杉材を使っており、使用材積は68.7立方㍍。床と階段の踏み板は5層5プライ、壁は3層3プライのものが使用されている。設計・施工は荒牧建設(福島県須賀川市、荒牧幸雄社長)、集成材の製造及びCLTの加工は藤寿産業(同郡山市、蔭山寿一社長)。CLTは壁と階段を山佐木材、床は銘建工業が製造している。
今回の事業は林野庁の「16年度CLT建築物等普及促進事業」として採択。このなかでいくつかの実証事業や実験が行われている。例えば、使用された柱脚金物は中層大断面木造での柱脚金物の標準化を目指して腰原幹雄東京大学教授を委員長とする中層大規模木造研究会が開発したものを採用し、金物の標準化を実証的に検証している。
また、施設完成後にも2階と3階のCLT床の遮音性能の検証を行う。床パネルはそれぞれのCLTのみの音響測定を行った後、2階CLT床には50㍉のALC、3階床には30㍉のモルタルを仕上げとしてそれぞれ施工。CLTのみの場合と同様の音響測定を行うことで遮音性能の違いを比較検証し、大型施設での防音に関する研究に活用する。
2017年12月2日(土)
Aパネ工法(木造在来軸組+CLT)構造見学会
岐阜の在日大韓基督教会岐阜教会にて
当社が製造している厚さ36mmのCLT(Aパネ)を木造在来軸組の構造用面材として利用した「Aパネ工法」の構造見学会が開催されます。
・開催日時:2017年12月22日(金)10:00~16:00
※時間内自由に見学可能です。①13:00~、②15:00~、2回解説の時間を設けます
・場所:在日大韓基督教会 岐阜教会(〒502-0041 岐阜市長良海用町1-15-1)※駐車場有
・参加費:無料
・設計施工:阿部建設㈱
・参加申込:「参加者氏名」「連絡先」「到着時間予定」を事務局へメールしてください。
・お問い合わせ先:Aパネ工法普及協議会事務局 https://www.apane-clt.com/ TEL 058-370-1884
2017年11月25日(土)日刊木材新聞より
◆中大木造担い手育成で要望書
林野庁には予算確保求める 日集協・CLT協会など10団体
日本集成材工業協同組合、日本CLT協会など10団体は20日、林野庁に対して中大規模木造建築工事の担い手の確保・育成に向けた「木質構造工事業」の創設及び資格・研修制度の構築に関する要望書を提出した。木質構造工事業ワーキンググループ(WG、佐々木幸久委員長=日集協理事長)が3回にわたる会合を経て取りまとめたもので、佐々木委員長、事務局の秋野卓生弁護士(匠総合法律事務所)らが沖修司長官に手渡した。その後、国土交通省の木造住宅振興室、建設業課へも提出した。
求めたのは「中大規模木造建築工事等の担い手の確保・育成に向けて、都道府県単位ではなく国レベルで、資格制度や研修制度、業者のグレード選定など、非木造と劣後しないような木造建築向けの資格・制度」を創設すること。
林野庁に対しては民間資格制度の構築に向けて来年度の概算要求に盛り込んだ関連予算の着実な確保、国交省に対しては建設業における「木質構造工事業」の創設の検討と鉄骨造分野に劣らない資格制度の構築、業界での活用を後押しする支援を要望した。
会見で佐々木委員長は「RCと木質構造、住宅と非住宅は設計も技術も異なるが、木質構造の非住宅にふさわしい資格がない。林野庁の来年度の予算が通れば、WGの委員中心に公募に応じ、有識者にもアドバイザーで入っていただきながら、しっかりした内実の伴った資格を作り、担い手育成に取り組みたい」と話した。
林野庁の宮澤俊輔木材産業課長は「住宅市場が成熟するなか、伸びしろは非住宅と考えられるが、誰に頼めばいいかを」"見える化"するものさしがないと普及には限界がある。業界が大同団結してこれだけのWGを作り、幅広い議論を経て提言されたことを喜ぶとともに、業界の声として真摯に受け止めたい」と話した。
要望団体は日本集成材工業協同組合、日本CLT協会、全国木材組合連合会、全国LVL協会、国産材製材協会、JBN、Aパネ工法普及協議会、木造施設協議会、中大規模木造プレカット技術協会、木構造テラスの10団体。
2017年11月10日(金)日刊木材新聞より
◆非木造と同等の資格制度求める
今月中に提言書提出へ 第3回木質工事業WG
第3回木質工事業ワーキンググループ(佐々木幸久委員長=日集協理事長)が2日、東京都内で開かれ、国へ提出する提言書の内容を固めた。「中大規模木造建築工事等の担い手の確保・育成に向けて、各都道府県単位ではなく国レベルで、資格制度や研修制度、業者のグレード選定など、非木造建築と劣後しないような木造建築向けの資格・制度の創設」を求めていくことで一致した。提言書は今月中にも国土交通省、林野庁へ提出する計画。
提言書の題名は「中大規模木造建築工事の担い手の確保、育成に向けた「木質構造工事業」の創設及び資格・研修制度の構築に関する要望書」に決まった。
過去2回の議論では、木質構造工事業の資格について1000平方㍍以上は1級、500平方㍍以上は2級など規模別の区分けが素案として示されたことなどから、「中大規模木造」の定義を巡って、「地域の工務店が取り組もうとしている500平方㍍以下の非住宅は対象に入らないのか」といった疑義も出た。だが、既存の住宅建築へは影響を与えないようにするとの狙いから、あえて「中大規模」と表現することが適当とし、資格の中身などの各論については来年以降の検討課題とした。
要望に挙げられた「鉄骨造分野における民間資格制度と同様の制度の構築」については、加工、木工事まで手掛ける大断面集成材メーカーが念頭にあることから、「施工だけ、加工だけの業者はどう位置付けられるのか」との疑問や「大工、工務店も取り組めるような内容にしてほしい」との要望が出された。
格付けの仕方については「特殊な加工機を持っているかどうかより材料の知識を含めて設計者からの相談に乗れることが重要。在来木造でも中大規模建築は可能なことから、資格・研修制度は在来の勉強も同時にできるようにする必要がある」「CLT建築も木造住宅の知識がないとできず、大きなピラミッドになるのではないか」との意見が出た。
資格については「規制法となれば、例えば500平方㍍以上は資格がないとできないなど力を持った法律となり、安心して頼める利点がある」「中小業者の排除ではないことを含みとして持たせる必要がある」との意見が出た。
2017年11月9日(木)日刊木材新聞より
◆6階建て事務所への採用実現
CLT使用建築物を報告 超高層ビルに木材を使用する研究会
超高層ビルに木材を使用する研究会(稲田達夫会長、事務局は山佐木材)は10月27日、鹿児島市内で第5回総会と記念シンポジウム「大規模木造施設へのCLT利用の課題と展望」を開いた。設計や大学、金融機関などから220人を超える出席者があった。
九州では、CLTパネルを使用した集合住宅や非住宅物件が現在、建設中の物件も含めて各県に1棟程度ずつそろいつつある。CLT生産を手掛ける山佐木材も、CLTの生産量拡大に向け加工機などを新設した。
シンポジウムでは松尾建設本店(佐賀市)や沖縄県下地島空港など、CLTを採用した実物件の担当者を招き、事業報告を聞いた。
松尾建設グループであるインフォメディア(佐賀市)の山崎心社長が登壇。2時間耐火の杉CLT床を実物件として初採用する松尾建設本店の新社屋について話した。
新社屋は延べ床面積3657.70平方㍍のS造6階建て事務所棟の2~5階床部分にCLT339立方㍍使用する。1フロアのCLT床の据え付けを1~1日半で終えたことなどを報告した。
三菱地所住宅業務企画部兼新事業創造部の三村翔氏は、沖縄県下地島に2019年開業を目指す空港施設について説明した。同施設はCLTを屋根構造として現しで表現する。空港ターミナルとして全国初のCLT採用建築物だ。白アリなどに対応するため京都大学監修の下、現在、防蟻実験を行っている。
塩屋晋一鹿児島大学学術研究院理工学域工学系教授は、自身が開発した鉄筋集成材「SAMURAI」について説明した。
同材は、山佐木材下住工場内に新設されたCLT工場棟の柱や梁にも採用されている。
稲田会長や三村氏、山崎氏、竹中工務店設計部構造部門長の麻生直木氏、三菱地所設計構造設計部の海老澤渉氏によるディスカッションも行われた。
2017年11月8日(水)日刊木材新聞より
◆CLT生産量を拡大
加工機新設、4年後に年間1万m3へ 山佐木材
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)が下住工場内に建設を進めてきたCLT工場棟とモルダーライン棟が完成し、11月中旬以降に本格稼働を始める。CLT工場棟に同加工機(ユニチーム)、モルダーライン棟にはモルダーやグレーディングマシンなどを導入した。同社のCLT生産能力は現在、年間で4000立方㍍。これを3年後に8000立方㍍、4年後に1万立法㍍まで引き上げる計画だ。またCLT工場棟の整備には、同社が普及に取り組む鉄筋集成材「SAMURAI」を活用した。
同社は、従来の生産能力では繁忙期などにCLTパネルの生産が追い付かないことがあった。加えて今後、長期的には全国でCLTの需要が増えることも見越して、今回、下住工場のCLTの製造ライン増強に着手した。
CLT加工機は3500×1万3500㍉までの加工が可能となる。同社論地工場もプレス機を1基から3基へ増設した。
CLT工場棟は木造平屋建てで、柱や梁にSAMURAIを使用。同集成材は杉構造用集成材の材長(繊維)方向に鉄筋を挿入することで、RC部材に匹敵する高剛性、高耐力の構造性能を発揮する。同棟では、最大25㍍スパンを飛ばした。
また桁行方向に2カ所ずつ、合計4カ所にCLTの耐力壁を設けた。2×4㍍のCLTパネル(5層5プライ)を3枚接合したもの。同棟の延べ床面積は1000平方㍍。
モルダーライン棟にはモルダー(トップスペック)とグレーディングマシン、含水率計(ともに飯田工業)、搬送装置(鈴工)が設置された。
従来、モルダー作業は5人で行ってきたが、今後は3人程度で対応できるようになり省力化にも寄与する。同棟も延べ床面積は1000平方㍍。
CLT加工機の輸入代理店は鈴工。今回導入された機械の販売窓口はすべて、山椎商会(鹿児島市)が担った。CLT工場棟とモルダーライン棟の新設及び機械導入には、昨年度(補正)の森林整備・林業木材産業活性化推進事業を活用した。
2017年10月14日(土)日刊木材新聞より
◆空港施設として初のCLT採用
1棟当たりで最大使用量 沖縄県・下地島空港
三菱地所(東京都、吉田淳一社長)は、沖縄県・下地島空港の旅客ターミナル施設整備で空港ターミナルとして全国で初めてCLTを採用した施設の建設工事に着手した。CLTの使用量は約1500立方㍍で、1棟当たりのCLT使用量としては日本一の規模になる見込み(日本CLT協会)。
下地島空港ターミナル施設では、CLTを屋根構造と壁の一部に使用する。沖縄県が定める地域材(沖縄県内で流通する県産または九州産材などの杉)を使用することで2017年度の林野庁CLTを活用した建築物等実証事業及び森林・林業再生基盤交付金制度を活用し、地域の森林・林業再生に貢献する。建物はRC造+CLT造の地上1階建て、敷地面積は3万1580平方㍍、施設面積は1万3840平方㍍。ラウンジ棟の陸屋根にはCLT420㍉厚と5層7プライ210㍉厚を2枚重ねて2方向のCLTフラットスラブとして構成する。チェックイン棟は寄棟屋根にCLT210㍉厚5層7プライを使用する。施工者は國場組、大米建設、特定建設工事共同事業体で、CLT工事は山佐木材、設計は日建設計。空港ターミナル施設はネット・ゼロ・エネルギービル(ZEB)として1次エネルギー消費を国の基準から68%削減する。BELS(建築物省エネ性能表示制度)で最高ランクの認定を受ける。
下地島空港は宮古島伊良部地区の旅客ターミナル施設として整備し、国際線・国内線旅客の取り扱い、プライベート機の受け入れなどを行うことで、17年3月に基本協定を締結、着工した。施設は19年3月開業を予定している。
2017年10月12日(木)宮古毎日新聞より
◆下地島空港 旅客施設が着工 三菱地所
国内外エアライン誘致 19年3月開業目指す
三菱地所(東京都、吉田淳一社長)は11日、下地島空港における旅客ターミナル施設整備事業を着工させた。2019年3月の開業に向けて国内外のエアラインと交渉を進めており、中期的には台北、香港、ソウル、上海からの定期便就航を計画している。国内線は都市圏からLCCの直行便を誘致する。開業初年度の誘客目標は5.5万人。
ターミナル施設は鉄筋コンクリート造の地上1階建て。敷地面積は3万1580平方㍍、建物面積は1万3840平方㍍となる。
エコの取り組みとして板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大判のパネル「CLT」を屋根の構造材に使う。1棟当たりのCLT使用量としては日本一の施設になる。
「空港から、リゾート、はじまる。」をキーコンセプトに掲げており、自然の光や風を取り込む構造でリゾート感を演出する。
設計は日建設計、施工者は國場組・大米建設特定建設工事共同企業体、CLT工事は山佐木材が行う。
開業後は国際線、国内線の両方を呼び込む。担当者によると、国際線の中期目標として当面は台北と香港をターゲットにする。ソウルと上海にも視野を広げていく。国内路線は成田、関空、中部それぞれからの直行便就航を目指す。
トゥリバーのリゾート開発とリンクさせて相乗効果も狙う。プライベートジェットの受け入れも前提に施設利用の拡大を図る。
安全祈願祭が11日、下地島の建設現場であった。三菱地所や施工業者などから関係者役60人が参加し、工事の安全と事業実施に伴う圏域の発展を祈願した。
三菱地所の谷沢淳一執行役専務は「空港に降りた瞬間から宮古諸島の豊かな自然環境を肌で感じてもらえるような施設にしたい」とコンセプトを強調。「高度な空港施設を生かし、宮古空港とも連携しながら島全体の発展に寄与したい」と意気込みを語った。
宮古島市の長濱政治副市長は「下地島空港の旅客ターミナルを起点に、島がますます発展することを期待している。市の観光振興において大きな力を発揮してくれるものと思う」と着工を喜んだ。その上で「市としては、2次交通など受け入れ態勢の課題解消に努めていきたい」と述べた。
2017年9月15日(金)日刊木材新聞より
◆賃貸集合住宅をCLTで
パネル工法に県産杉 センチュリーハウス
鹿児島県姶良市に、同県初となるCLTパネル工法による物件が建てられている。センチュリーハウス(鹿児島市、加治木百年社長)の3階建て賃貸集合住宅「センチュリーマンション」だ。一部に鹿児島県産杉CLTを使用する。燃えしろ設計で準耐火構造。壁の一部が現しとなっている。山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)と銘建工業(岡山県真庭市、中島浩一郎社長)がCLTパネルを供給した。
同物件は延べ床面積660平方㍍で12世帯が入居できる。一番大きな壁は高さ3000×幅2000×厚み150㍉で5層5プライ。銘建工業は2,3階の床の一部に5層5プライのCLTパネルを供給した。CLT床は、山佐木材も加工した。
木材は鹿児島県産杉を含めて230立方㍍を使用。そのうちCLTは213立方㍍だ。集成材の使用量は6.85立方㍍で、Rウッド集成材や杉集成材を使っている。
外周りはウレタン断熱材を吹き付け、外壁はサイディングとなる。
設計はオカモト都市設計(鹿児島市)、施工はセンチュリーハウスが担当した。工期は今年7月から同11月までの予定。建築に当たり、昨年度のCLT利活用加速化事業の補助も活用した。
センチュリーハウスは、木造で年間着工100棟程度の地場ビルダー。同県では将来的な人口減などが予想されるなか、CLTを新規事業として伸ばすことも視野に入れている。
加治木社長は「今回、CLTパネル工法は施工が簡単で、驚かされた。建築コストも、現状ではRC造比で15%程度下がるのではないか」と話している。
鹿児島県も同工法を普及させていきたい考えだ。11日には、県内外の行政担当者や建築、設計者を対象に、同物件の構造見学会を開いた。普及への取り組みとして、今年は佐々木幸久社長などが登壇するシンポジウムを開催。木造の建築士を集めた研修会なども含めて、情報発信を行っている。
2017年9月12日(火)南日本新聞より
◆CLTパネル普及を
姶良 県主催見学会に200人
木造高層建築が可能な直交集成板(CLT)を使った集合住宅の構造見学会が11日、姶良市であった。普及を図ろうと県が主催した。県かごしま材振興課によると、CLTパネルを使った建築物は県内初。行政や民間技術者など、県内外から約170人が視察した。
CLTは、繊維が直角に交わるように木板を積み重ねて接着した建材。強度が高く、欧州を中心に広く普及する。日本でも2013年度に日本農林規格(JAS)認定が始まり、国産材利用の切り札として期待されている。
見学したのは、センチュリーハウス(鹿児島市、加治木百年社長)が施工する3階建て賃貸集合住宅で、延べ床面積660平方㍍。木材は230立方㍍使用し、うち213立方㍍を占めるCLTパネルは山佐木材(肝付町)が供給した。7月中旬から着工し完成予定は11月末。同等の施設を鉄筋コンクリートで造ると、工期は6カ月が目安だという。
加治木社長(49)は「使い勝手の良さに驚いた。より高層の建物で使いたいし、顧客にも積極的に提案したい」。県かごしま材振興課の米森恒司課長は「施工実績が少ないため、多くの人の目に触れるモデルになってCLT利用の裾野が広がれば」と話した。(川野裕和)
2017年9月8日(金)日本経済新聞 九州・沖縄経済面より
◆次世代の建材 CLTに商機
鹿児島の山佐木材 5億円で設備
直交集成板(CLT)は大規模木造建築用の新たな建材として注目されている。断熱性などに優れており、山佐木材(鹿児島県肝付町)は国内有数のCLTメーカーだ。合計で約5億円を投じる新たな生産設備を10月末にも稼働。年間生産能力を1万立法㍍と現在の2.5倍に引き上げる。競合他社の動きもにらんで生産体制を整え、需要をつかもうとしている。
欧米で普及先行
鹿児島市内から車で2時間弱。同社の主力拠点である下住工場(同)は大隅半島の中ほどにある。CLTは現在、下住工場で作った板材を論地工場(同)でプレス加工し、納入先のニーズに合わせて切削加工して製品に仕上げている。今回の設備増強では板材の生産能力を高めたり、切削加工に用いたりするラインを下住工場に増設。論地工場にある3台のプレス機もフル稼働させる。
CLTは欧米を中心に普及が先行しており、中・大規模のマンションや商業施設などの壁や床に用いられている。日本では2013年に日本農林規格(JAS)が制定された。「日本再興戦略改訂2014」には国産材CLTの普及加速を図ることが盛り込まれた。16年にはCLTを用いた建築物の一般的な設計法等に関し、建築基準法に基づく公示が公布・施行。告示に基づく構造計算などを行えば、国土交通大臣認定を個別に受けることなく建築確認によって建築が可能になった。
山佐木材がCLT生産を始めたのは14年。16年にはCLT床2時間耐火構造の大臣認定も旭化成建材(東京・千代田)と共同で取得した。ただCLT業界の盟主である銘建工業(岡山県真庭市)との事業規模の差は大きい。サイプレス・スナダヤ(愛媛県西条市)も原木からCLTまで一貫生産する新工場を来春から稼働させる予定だ。
全国で利用増へ
山佐木材の佐々木幸久社長はそうした状況を冷静に分析。同社は九州ではCLT分野で先駆的な存在だが「九州・沖縄地区を含め、今後は全国で建築へのCLT利用が進む」と考えて、生産体制強化に踏み切った。
実際、九州地場最大手ゼネコンの松尾建設が佐賀市内で取り組んでいる新しい本店社屋の建設では事務所棟にCLTの床材を採用。山佐木材はパネルの加工・施工を担当する。住宅メーカーのセンチュリーハウス(鹿児島市)もCLTを使う賃貸集合住宅を鹿児島県姶良市に建築中だ。
山佐木材は1948年に山佐産業として創業し79年に同社から分割して設立した。2017年4月期の売上高は約22億円。1987年から社長を務める佐々木氏は71歳になったが「CLTを製材、大断面集成材に続く3本目の柱に育たなければ」と意気軒高だ。鉄筋で補強した集成材「SAMURAI」の実用化にも取り組んでいる。当面は経営の第一線に立ち続けることになりそうだ。
(鹿児島支局長 松尾哲司)
2017年8月8日(火)メルマガ臨時号
超高層ビルに木材を使用する研究会:第5回総会およびCLTシンポジウム開催いたします
■日時:10月27日(金)12:30~会員受付開始、13:30~一般受付開始
■場所:鹿児島大学 稲盛会館 キミ&ケサ メモリアルホール
■内容
(1)13:15~13:45 総会
(2)14:00~14:10 シンポジウム開会、主催者挨拶、来賓挨拶
(3)14:10~15:00 特別講演
<特別講演1>「ヨーロッパを中心とした木造建築の潮流」
鹿児島大学工学部建築学科准教授 鷹野 敦氏
<特別講演2>「鉄筋集成材SAMURAIによる山佐木材CLT工場棟の設計と建設」
鹿児島大学工学部建築学科教授 塩屋 晋一氏
(4)15:10~17:30 パネルディスカッション「大規模木造施設へのCLT利用の課題と展望」
(5)18:00~20:00 意見交換会 鹿児島大学内エデュカ(教育学部食堂)
■参加費:無料(※意見交換会は会費5,000円を予定)
■定員:150名 ※会員優先、会員外は先着順 ※定員に達したため受付終了しました
■申込:下記ご案内をダウンロードいただき、参加申込書ご記入の上、事務局へFAXしてください
※申込締切 9月22日(金)
※シンポジウムの翌日10月28日(土)、希望者にエクスカーション(山佐木材工場見学)を予定しております。詳細・申し込みは下記ご案内を参照ください。(定員50名) ※定員に達したため受付終了しました
2017年8月1日(火)日刊木材新聞より
◆CLTで九州支所の実験棟建設
研究用施設で国内発 森林総研
森林研究・整備機構森林総合研究所(森林総研)は、九州支所(熊本市)の共同特殊実験棟をCLTパネル工法で建てることを決定し、今月着工した。既存の実験棟は鉄筋コンクリート造だが、建て替えるに当たり、研究用施設の建築としては国内で初めてCLTを採用した。来年1月の竣工を予定している。
実験棟は2階建てで、昨年施工された告示にのっとり、床、壁、屋根にCLTを用いるパネル工法で建てられる。延べ床面積は、1424平方㍍、1階は実験室、2階は書庫などとして使われる。
CLTは国産材で製造され、約600立方㍍が使われる予定。供給は山佐木材と銘建工業が行う。実験棟に隣接して在来工法で木造の倉庫も建設される計画で、総事業費は6億7000万円。設計者はE.P.A・永園・山佐設計共同体で、工事は上山建設(長崎県東彼杵郡)が行う。
森林総研の九州支所と九州育種場の建物や設備は昨年の熊本地震で損傷、林野庁は2016年度第2次補正予算で森林総合研究所災害復旧事業(施設整備費補助金)10億5000万円を計上した。
同予算を受け、九州支所では、研究本館他9施設の修繕と設備の更新・修繕を行っているところだが、実験棟は損傷が著しいため建て替えとなった。森林総研は、熊本地震からの復興に当たり、CLTパネル工法を積極的に採用することで、CLTの普及に寄与したいとの考えから、建て替えに当たりCLTパネル工法を採用した。
CLTが立ち上がる秋頃には現場見学会も予定している。塗装は外壁材で覆われるが、内装は一部CLTを現しで残す予定で、完成後もCLTを見ることができるようにする。
2017年7月12日(水)日刊木材新聞より
◆狭小地でCLT活用
準防火地域で準耐火建築物として設計
CLTパネルを活用した「(仮)柳町CLT Build」(高知市)が6月末に完成した。CLTパネルを耐力壁に使い、床板と木造軸組工法を組み合わせてフレーム構成した準耐火建築物で、事業主体はエスティハウス。都市部狭小地における建築工法の選択肢の一つとしてのCLTの優位性を実証するため「CLT建築推進協議会」と連携して進めたプロジェクトだ。
同建物の敷地面積は106平方㍍、3階建て、延べ床面積は243.91平方㍍(CLT47.38立方㍍、その他34.08立方㍍)。CLTは壁、床、屋根に採用した。
高知市の都市部狭小敷地(繁華街)に建てられた複合ビルで、特徴は準防火地域にあるため、準耐火建築物として設計されたこと。耐力壁のCLTは燃えしろ設計(石膏ボード等で被覆しない)で幅150㍉(45分で45㍉が燃焼しても残り105㍉で自立する設計)。室内にはCLTを現しで使用している。
1階は飲食店として使用されることになっており、10月にオープンする予定だ。木材を生かした店舗デザインが期待されている。上層階の外観は、ガラス越しに内部のCLT壁が見えるようになっており、夜間はCLT壁がライトアップされる。
設計事務所は、建築設計群無垢(高知市)が意匠、桜設計集団一級建築士事務所(東京都)が構造を担当し、CLT建築推進協議会が設計支援を行っている。
2017年7月6日(木)日刊木材新聞より
◆2時間耐火の杉CLT床を初採用
佐賀市の松尾建設本店 山佐木材と旭化成建材の国交大臣認定で
杉CLT床を実物件として初採用した建築物が佐賀市内に建設中だ。山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)と旭化成建材(東京都、堺正光社長)が共同で国交省大臣認定を取得した2時間耐火構造を採用。松尾建設本店(佐賀市)の新築移転に伴うもので、S造の事務所棟の2~5階の床部分に使用される。今月末から、CLT部分の工事に入る予定だ。
CLTには九州産杉を使用し、主なサイズは厚さ210×(7層)×幅1600×長さ3200㍉が160枚。210×1600×4000㍉が56枚、210×2000×4000㍉が48枚だ。CLTの使用量は328立方㍍となる。
松尾建設は、佐賀市内に延べ床面積3657.70平方㍍のS造6階建て事務所棟と同987平方㍍の木造2階建て会議室棟を建設する。会議室棟に使用する木材には、佐賀県産材を最大限活用した。山佐木材が事務所棟のCLTパネルの加工および施工、会議室棟の木造工事(軸組工法)の施工を担当する。
非木造建築のなかで杉CLT床を採用することにより建築物の軽量化を図れた。松尾建設は今後、敷地条件や建物用途、規模などを勘案し、杉CLT採用の提案を検討していく。
一方、山佐木材は杉CLTの需要先として住宅や非住宅はもちろん、今回のような非木造建築分野での部分的利用に積極的に取り組んでいく考えだ。
同社は今年度中に同材の製造ラインの集約化・増強を図り、年間生産能力を1万立法㍍まで引き上げる。論地工場ではプレス機を1基から3基に増設中だ。
また、下住工場内に、同社が普及に取り組むSAMURAI集成材を使用するCLT加工棟とラミナ加工棟が今秋完成の予定だ。同集成材は杉構造用集成材の材長(繊維)方向に鉄筋を挿入することで、RC部材に匹敵する高剛性、高耐力の構造性能を発揮するもの。CLT及びラミナ加工機も新設される。
2017年6月20日(火)日刊木材新聞より
◆木軸+CLTの新工法モデルハウス
宿泊体験の場として活用開始 阿部建設
阿部建設(名古屋市、阿部一雄社長)は昨年4月、同市守山区の大森エコタウン内にCLTを活用したモデルハウス「手しごとの家」をオープンした。林野庁の森林整備加速化・林業再生事業(CLT等新製品・新技術実証・展示加速化事業)の補助を受けたもので、新しい建築需要の開拓に期待を寄せている。現在は在来木軸+CLTの「Aパネ工法」の実証モデル棟として位置づけられており、宿泊体験館としてもこのほど運用を開始した。
同モデルハウスは、木造軸組工法による2階建て(延べ床面積約162平方㍍)で、壁や床には長さ3000×幅1000×厚さ36㍉の国産杉製JAS認定CLT(鹿児島県の山佐木材による製造・加工)を合計109枚使用している。非住宅物件を想定・対応するため階高を高く設計し、CLT耐力壁や自然素材の採用等により木の質感あふれる堅牢な建物となっているのが特徴だ。特に、CLTの採用は断熱性・遮音性・耐火性の確保につながり、これにOMソーラーライトとクワトロソーラー、太陽光発電などを組み合わせてZEH仕様を実現した。
同社ではCLT利用について、NPO法人WOOD ACや岐阜県立森林文化アカデミー等と連携して木造軸組工法用のCLTによる耐力壁や水平構面の構造試験を実施。各標準仕様を決定して設計・施工要領書を整備し、同モデルハウス建築を通じて設計・技術・施行を検証する。特に耐力壁の総数を減らせる点や一般的な施工方法で建築が可能な点、間柱の省略で空間を有効活用できる点などをメリットとして挙げている。現在、同工法はAパネ工法普及協議会(阿部一雄代表)が中心となって普及に取り組み、木造のコンビニ店舗など非住宅の建築需要に的確に対応できる工法としてPRしている。
2017年6月22日(木)日刊木材新聞より
◆文化財修復に集成材活用
歴史的建造物での事例紹介 日集協が研究会
日本集成材工業協同組合(佐々木幸久理事長)は14日、東京都内で第3回「文化財などの復元・修復に向けた集成材等利用研究会」を開いた。上田忠司竹中工務店設計本部アドバンストデザイン部伝統建築グループ課長が講演した。
上田氏は、集成材のルーツは仏像の寄せ木造りだとした。寄せ木造りにより分業体制ができ、漆や糊などを使って接着されたことで長期保存も可能になったという。1705年に発明された組柱では、芯柱の周りにピースを張って金輪で留める。出雲大社の16丈(約30㍍)もある柱も3本の丸太を合わせて金輪でつないでいたと考えられている。松江城の柱は角材の芯を板で囲い金輪でバインド、木材同士はかすがいで留めていたなど、伝統的な建築物のなかで集成された木材の歴史を解説した。
文化財保存の世界的な流れは、1931年のアテネ憲章が基本原則になり、64年のベニス憲章で歴史的な証拠として残す考え方が示された。72年に世界遺産条約で意匠、材料、技術、環境など真正性の要件が挙げられ、99年にイコモスが歴史的木造建築物保存の原則を示した。
日本では消耗材としての屋根葺き材などで本来の樹種ではない木材や外材が使われるケースがあり、文化財として価値のない場合は材料にこだわる必要はないとの解釈を示した。
上田氏は私見として、集成材利用は小屋裏、床下などの構造補修材、大径材活用の代替での使用はあり得るとした。小屋裏などでは一般木部との取り合いを考慮し、接着剤は伝統・自然材に由来するものだと抵抗感は少ないとした。
2017年6月21日(水)日刊木材新聞より
◆木質構造工事業の創設へ
年内提言に向け議論開始 木質構造工事業ワーキンググループ
中大規模木造建築物などの加工、工事を担う専門工事業創設に向け、木質構造工事業ワーキンググループが14日に第1回ワーキング(WG)を開いた。委員長に佐々木幸久日本集成材工業協同組合理事長が就任した。関連業界11団体が集まり、専門工事業の創設の必要性について議論。3回の開催で提言をまとめることとした。
冒頭、このWGの呼び掛けを行った佐々木氏が、自社(山佐木材)で約20年前から大規模木造建築物の設計、加工、工事に取り組んできた経緯を述べた。中大規模木造建築物に取り組む施工技術者は全国で500~
700人程度だとし、今後、中大規模木造建築物の市場が拡大していくなかで技術者が300人以上不足するとの懸念を示した。また、「大規模木造の工事では、チェンソーを使って荒削りするなど(住宅との)仕上げの違いが大きく、腕のいい住宅大工ほど抵抗が大きかった」ことから、大規模、大断面木造に特化した施工技術の必要性を感じたとし、新たな専門工事業の創設の必要性を主張した。
事務局を務める秋野卓生氏(匠総合法律事務所代表弁護士)は、行政側との事前協議で建設業許可業種「大工工事業」に包括したまま担い手育成が可能かを相談。木質構造工事業を担う技能士等に特化した技術者資格の創設を国に提言するか、団体として技能士等の育成を行い、主任技術者として認めてもらうかなどの提案を受けたことを説明した。委員からは、技能士制度は民間工事では必須とはならず、専門工事業としての創設を目指したいとの意見があった。
担い手育成に取り組む団体も参加。青木哲也JBN中大規模木造ワーキング主査は、住宅建築の延長上にある4号建築物、量産が可能な店舗・倉庫、木造化が望ましい学校・医療施設・高齢者施設などの施工を担えるよう取り組んでいるとした。Aパネ工法普及協議会は36㍉の薄型CLTを壁倍率5倍で使った工法を供給する団体として設立した。阿部一雄代表が社長を務める阿部建設(名古屋市)では、工務店4社で「名工家」という一般社団法人を設立。大工職人の協力関係を構築し、6月から4社の下請け業者職人500人のスケジュール管理を共有化する取り組みも始めた。木造施設協会は5月に設立し、今後、工務店連携で1000平方㍍以下の木造建築物に取り組んでいくことを相羽健太郎代表理事が報告した。
行政からは、古沢弘康岐阜県県産材流通課技術課長補佐兼係長が非住宅木造建築物向けの人材養成講座を今年秋ごろから始める計画を説明した。高知県は、林業大学の開校を通じて木材に通じた建築士の育成にも取り組んでいくことを小野田勝東京事務所チーフが報告した。
意見交換では稲山正弘中大規模木造技術プレカット協会代表理事が、在来工法は仕口・継ぎ手の締まりはめ、大断面木造は鋼板挿入ドリフトピン施工の隙間はめと技術的な違いに言及。近年開発された金物工法は締まりはめ工法に近くなっており、双方の技術が融合しつつあるとした。在来工法では単純梁、大断面木造では組み立て梁・トラス・アーチなどの架設の仕方も違うなどの意見があった。徳盛岳男全国建設労働組合総連合住宅対策部長は、木質構造は2×4工法、CLT、LVL、集成材などそれぞれ施工基準、接合部が異なるとし、単一の技士で対応することに疑問を呈した。そのうえで、技術をランク付けしてそれに応じて単価が上がる仕組みなら必要との意見を述べた。
WGは年内にあと2回開き、提言をまとめていく。
2017年6月3日(土)日刊木材新聞より
◆17年は2万m3供給見込む
技術開発状況を報告 日本CLT協会
日本CLT協会(東京都、中島浩一郎会長)は、5月30日に東京大学弥生講堂一条ホールで「技術報告会2017」を開き、約270人が参加した。中島会長は「一般社団法人化して3年になる。昨年告示が出て、12ワーキンググループ(WG)で解説書作成などに取り組んできた。今回はWGの活動を知ってもらうために報告会を開催した」と会の狙いについて話した。
CLTは昨年告示化されるとともに、2015年度には「CLTで地方創生を実現する首長連合」が発足、16年5月には「CLTで地方創生を実現する議員連盟」と「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」が発足するなど、CLTの普及に向けた動きが加速度的に進んでいる。これまでに国内ではCLTパネルを用いた建築物が完成70棟、着工予定70棟を数える。国内生産量は12年の200立法㍍から、16年には5000立方㍍となり、今年は2万立法㍍を見込んでいる。国内でJAS認定を取得している協会会員CLT工場は7工場(オホーツクウッドピア、西北プライウッド、中東、レングス、銘建工業、ウッドエナジー、山佐木材)、CLT加工工場は9工場(オノツカ、藤寿産業、ダイテック、志田材木店、中東、翠豊、スカイ、銘建工業、山佐木材)と供給体制の整備が進んでいることも示した。
標準仕様WGでは、「実務者のためのCLT建築物解説書」の発行に向けて作業しており、9、11月には講習会の開催も計画している。
遮音WGでは、床遮音仕様11での性能試験の実施、界壁遮音性能試験の実施とCLT150㍉片面現し仕様と両面現し仕様での界壁大臣認定取得を行った。
歩行振動WGでは、CLT床の場合は歩行振動を認知しやすいことから、対策用スパン表の作成に取り組んだ。北見、高知での実測データを基にモデル化を行い、検証実験も行った。
防耐火構造WGでは、窯業系サイディング外壁仕様と木製外装材仕様の2仕様で防火構造試験に合格。防火被覆を行ったCLT壁にスイッチ、コンセントボックスなどを取り付けるケースで試験を行った。
製造・加工WGでは、CLTのJAS改正に向けて要望事項を検討、CLTの寸法安定性確認試験での反りデータの蓄積を行った。CLT製造から、現場施工に至る期間の養生方法なども考慮。さらにCLTの加工に用いるCAD/CAMデータフォーマットの意匠CADとの連携や、鉄骨造の設計に使うIFCとの将来的な連携の可能性などにも触れた。
接合WGでは、住木センターのx(クロス)マーク金物はCLTの外部に露出することから、意匠性や燃えしろ設計対応などの面で被覆型金物を検討し、xマークへの追加なども求めていきたいとした。
施工技術合理化WGでは、国土交通省官庁営繕部の木造標準仕様書にCLTを追加してもらうことを目的とした、施行手順や施工精度などの確保に向けた取り組みを紹介した。CLTは大判で現場の施工計画を立て、重機の配置や仮置き、地組みの仕方なども検討しないと効率が低下すること、アンカーボルトの施工精度の確保の重要性などを示した。
温熱WGでは、CLTの熱伝導率が明確になっていないが、天然木と合板の中間程度の値になるのではないかとの見通しを示した。つくばの実験棟での気密性能を検証したところ、パネルの隙間、金物の切り欠き部などで機密施工を行うとC値(隙間相当面積)は9.7から2.6に改善した。CLTは熱容量が大きく、室温の安定や調湿機能が期待できること、断熱性能は高いが、省エネ性能を確保するため建設地に応じた断熱施工を行うこと、緊結金物周辺の機密施工なども必要と報告した。
耐久性WGでは、CLTの防腐・防蟻処理については基準が未整備だとし、材料は製材JASにより芯材を使用するか、保存処理K2以上かAQ3種以上(構造用集成材)に加えて、排水対策を行う必要性も示した。
広報・普及WGでは、昨年の欧州視察の状況を報告した。
2017年5月31日(水)日刊木材新聞より
◆需要創出・人材育成に取組む
日本集成材工業協組・通常総会
日本集成材工業協同組合(佐々木幸久理事長)は19日、東京都内で第46回通常総会を開いた。今年度は引き続き文化財などの復元・修復に向けた集成材利用の推進や大断面集成材の利用拡大に向けた規格化の検討を行うほか、造作用集成材の新たな利用による需要の創出、中層大規模木造建築物の躯体工事を担う人材の育成などに取り組むことが決まった。また、新理事に田中太郎セブン工業社長の就任が承認された。
佐々木理事長は「昨年度は住宅建設がおう盛で、会員の方々も恩恵を受けた型が多いと聞き、喜んでいる。とはいえ、先行きには幾つかの懸念があり、集成材の品質管理、新しい技術開発や需要開拓、担い手の育成、確保など課題も多々ある。これらについては鋭意取り組みを進めているところで、手腕不足で至らぬことも多いが、辛抱強くご指導をお願いしたい」とあいさつした。
昨年度の事業報告では、集成材の自主的な強度調査(11社11品目77体)の実施や岡山県真庭市での技術研修会の開催EPA交渉を巡る必要な国境措置の要請活動の実施活動が報告された。
来賓祝辞では、前田武志日集協顧問、宮澤俊輔林野庁木材産業課長、澁谷浩一国土交通省木造住宅振興室長、前田直登日本林業協会会長、古久保英嗣日本住宅・木材技術センター理事長があいさつした。
2017年5月19日(金)日刊木材新聞/「新・国産材戦国時代インタビュー」より
◆今こそ過伐対策を
大中型木造を確固たる需要分野へ
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は、1991年に日本で初めて杉の構造用集成材JAS認定を取得して大中型木造建築事業を始めるとともに、業界に先駆けて設計、施工体制構築まで踏み込み、同分野の需要拡大に貢献してきた。昨今も杉CLTのJAS認定、またCLT床耐火2時間構造認定を取得し、住宅、非住宅(大中型木造)に続いて非木造建築分野での木材、国産材需要開拓につなげることを目指している。だが、佐々木社長が今、最も関心を寄せるのは、我が国の持続的林業経営が可能かという点だ。現状は過伐状況と見て早急な対策が必要だと話す。
様々な分野で国産材需要が拡大しているのは喜ばしいことだが、九州など素材生産先進地では過伐状況になっており、持続的林業が不可能になってしまうのではないかと懸念している。再造林率の統計は出ているが、実際の有効林分率などを掛け合わせると、将来生育してくる資源量は表面上の数字よりもかなり低いのではないかと考えざるを得ない。また、資源はあっても手の入っていない山が大量に残るという可能性も大きいと思う。
国産材が利用期に入った今こそ、放置林に対する法的な対応が必要ではないか。しっかりとした林業を行っている事業者には手厚い助成を、そうでない場合は罰則を作るくらいで臨まないと、結局、将来に大きなツケを残す。膨大な経費を使って対応策を講じなければならなくなるだろう。
欧州などでは、しっかりとした資源調査の下で年間伐採量を決定しているところが多い。厳格な運用の下でも素材生産量を伸ばしている国がある。我が国でも同様のことができないはずはなく、間伐を中心にした循環型林業により、森林の公益的機能維持と素材生産量増加の両立は達成できると思う。日本でもフォレスター制度が始まり今後の主導的な役割を期待するが、早期に手を打っていくため、当初は行政の関与が必要だ。
民間企業としても取り組みを進めている。地元の森林組合と原木直納契約を結ぶなかで、再造林が確実に行われている林分からの出材を条件に盛り込んだ。森組側も再造林の促進につながるとして積極的に取り組んでくれている。また、地元行政にも働き掛け、官民連携による持続的林業実現への方策を推進している。今後は産官学で現実的に林業が利益を出せる方策を提案するための研究会を始めたいと思っている。
安心できる木造の発注環境整備を
大中型木造建築、また非木造建築のなかで木材利用を広げていくためには、設計、施工側が安心して仕事を発注できる環境を整えることが必要だと考えている。東京オリンピックなどはその大きな契機となる可能性があり、木材業界がしっかりと対応できれば、従来、同分野でも確固たる需要を獲得できるようになっていくのではないだろうか。日本集成材工業協同組合(佐々木氏が理事長を務める)でも、人材育成を含めて取り組んでいきたい。(連載は来週につづく)
2017年3月28日(火)日刊木材新聞より
◆再造林を原木契約購入の条件に
林業の持続的経営実現へ地元から取組む
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は、製材用原木の直納購入部分で、素材生産事業体側と再造林が行われていることを条件とした供給契約を行う取り組みを進めている。既に曽於地区森林組合からは年間2万5000立方㍍(月間2000立方㍍強)の供給体制となり、鹿児島県森林組合連合会とも年間3000立方㍍の契約を行った。同社の原木消費量は年間5万立方㍍前後になるため、再造林が確実に行われている原木の使用比率が過半を超えてくることになる。
同社は杉大断面構造用集成材、同CLTなどの製造、販売、また設計を含めた木造建築への対応に時代に先駆けて取り組んできたメーカー。また、ビルダ向けの中小断面構造用集成材、協同組合きもつき木材高次加工センターでは杉KD構造材、羽柄材などの量産も手掛けている。
現在、国産材先進地の九州では製材・集成材、合板、輸出、発電用など国産材需要が増加。これに伴い、素材生産量も拡大するなか、同社の佐々木社長は統計上に現れない有効林分率、再造林率などを考慮していかなければ、林業の持続的経営が危機に陥ると懸念している。そこで、まずは地元から再造林を推進するための様々な方策を模索しており、今回の取り組みはその一環となる。
原木の安定供給に向け、同社は曽於地区森組との原木直納契約を開始したが、そのなかで両者の考え方が一致し、契約数量分の再造林が確実に行われていることを条件に盛り込んだ。森組側も再造林の促進につながるとして積極的に取り組み、当初の契約量は月間1500立方㍍だったが現状では月間2000立方㍍強が供給されている。新たに同様の契約を結んだ鹿児島県森連を含め、同社は今後も行政、素材生産事業体などと連携し、林業の持続的経営の実現に寄与していく考えだ。
2017年3月22日(水)日刊木材新聞より
◆CLT活用建築物の成果を報告
多様な実例で課題を浮き彫りに 木構造振興
木構造振興は日本住宅・木材技術センターと14、15の2日間、東京・豊洲シビックセンターホールで「CLT活用建築物等実証事業成果報告会」を開いた。同報告会は2015年度補正地域材利用拡大緊急対策事業と16年度新たな木材需要創出総合プロジェクト事業の補助を受けて行ったもので、CLT建築物の設計や施工方法などの開発や工夫、コストなども報告した。
報告会では「CLTを用いた既存木造住宅の耐震補強」について岡本滋史島根大学大学院講師が、配管用に穴開けしたCLTを使用するために行った実験、面内せん断性能試験の報告をした。築34年の木造住宅に精密法による耐震診断を行い、1階は短手方向の壁が少なく偏心が大きいことからCLT3層3プライ(厚さ90、幅1400、高さ2700㍉)を3枚壁に使用し、既存住宅の梁下端にL型金物を付けて20㍉のクリアランスを設けて挿入。足下はM16㍉のアンカーボルトを設置した。2階は合板耐力壁を設置し、耐震性能を補強前の8倍以上、現行の建築基準法を満たすことができた。
「高知版CLT〈ゆかばい90〉設計・性能実証事業」の報告では、立道和男高知県中小建築業協会会長が木造住宅における2階床等剛床パネルとしてCLTを使用するために行った実験について報告。上部構造の構造躯体が水平力に対して安全であることを示すのに住木センターのグレー本で示されている詳細計算法を使って実証モデルを用いた構面実験で確認した。同協会のグループでは年間700棟の木造住宅を供給しており、CLTも住宅の床として水平構面を固め長期優良住宅として耐震性能を高めていくこと、耐震改修は年間1000件くらいで実施し、4㌧車で現場搬入して施工できるよう取り組んだ。
「大牟田の整骨院併用住宅新築工事の建築実証」では、鷹野敦鹿児島大学准教授がCLTパネル工法で戸建て住戸付き診療所をCLT告示によるルート2で設計。合掌組みのCLTパネル工法で独立したユニットとして成立するように、梁間方向を三角形とし軸力系のみの伝達にして、桁行方向は無開口の壁とする。平屋建て延べ床面積109平方㍍でルート1の掲載でも対応できるが、仕様規定では過大な接合部の仕様が求められるため、あえてルート2の設計法で対応した。
「井上ビル新築工事の建築実証」では、梅野光太郎大匠建設建築部主任が2階建て延べ床面積400.16平方㍍のCLTパネル工法での建築について説明した。施工はアンカーボルト205本を精度よく施工するために、コンクリート打設前に型枠の天端にフラットバーを設置してアンカーボルトの設置位置を微調整。床に使った5層7プライのCLTは1枚が700㌔もあり、25㌧クレーンを設置して対応。バルコニーはCLTの特徴でもある跳ねだしを1.8㍍行った。
敷地条件から25㌧クレーン車のアウトリガーが住宅内部に入らざるを得ず、1階の壁の一部の設置を後回しにして2階の建て方を先に行い、途中から13㌧クレーンに変えるなど工夫した。xマークの金物1800個、ビス3万2000本を使い、金物関係だけでも相当な費用になったことを報告した。
「若杉ヴィレッジヴァンガード新築工事の建築実証」では、日野雅司SALHAUS代表取締役が石川県で建設中の3階建て延べ床面積779.22平方㍍の建築について述べた。中規模マンションでは住戸の形状やプランなどが多岐にわたり、建物形状も複雑化するケースが多いことで多様な住戸プランに対応したCLTの採用により実践的な検証を行った。施工は事前にモックアップを作り検証したことで、建て方工期は1階フロア4日間、全体では約2週間で行い、1時間準耐火構造に対して床はすべて燃えしろ設計、間仕切り壁、非耐力壁は厚さ75㍉以上として性能を確保した。
「KFC堺百舌鳥店新築工事の建築実証」では、畑正一郎Sho建築設計事務所代表が世界的なファストフード店舗をCLTを使って建築した事例を報告。対象建物は延べ床面積161.11平方㍍の平屋建てで、狭い敷地に重機を入れるといっぱいになってしまい、1日分の施工材しか現場に搬入できない状況のなかで、4日間で建て方から屋根、外壁下地材まで施工し、S造の場合14日掛かる工期を短縮したことを報告した。
2017年3月4日(土)日刊木材新聞より
◆年間5万m3の需要確保が焦点に
不採用の理由、早急に調査を指示
CLTで地方創生を実現する議員連盟
昨年5月に発足したCLTで地方創生を実現する議員連盟(石破茂会長)は、2月23日に第3回総会を開いた。国内のCLT生産能力は年間5万立方㍍に達しているが、需要が追いついていないとの報告を受けた石破会長は、「国や自治体が建てる公共物件になぜCLTが採用されなかったのか、その理由を明らかにしなければ需要拡大策を進められない。コストが問題だったのか、従来と違う工法は手間が掛かると避けられたのか、そもそも検討されていないのか。早急に全省庁、全都道府県で理由を調べてほしい」と方針を示した。
内閣官房から2017年度のCLT関連予算やCLT活用物件数(進行中含む)、20年度までのCLT普及に向けた新たなロードマップについて説明があり、環境省の新しい補助事業に関心が集まった。ただ、20年東京五輪関連施設へのCLT採用については、新国立競技場では内装等に可能な限りCLTを使うことになっているが、その他の施設はIOCからできるかぎりコスト削減を求められているとの状況が報告された。
CLT活用物件数は今年1月26日時点で70件となり、昨年9月12日時点の38件から大きく増えていると報告された。
用途別の内訳は事務所が15件で最も多く、住宅と商業施設・倉庫等がそれぞれ14件、学校8件、介護施設5件と続いている。地域別では関東が23件で最も多く、ついで九州13件、北海道・東北と四国がそれぞれ8件と続く。
中島浩一郎日本CLT協会会長は、16年度末までに完成予定のCLT物件が62棟、17年度以降の予定が63棟で、宮城では10階建て集合住宅で鉄骨造の床にCLTを利用する新しい試みが進行中と報告した。「福島で建設予定のCLTの復興住宅は、協会として構造計算をはじめ全面的にサポートし、復興住宅のモデルとなる良いものを作っていきたい。16年度のCLT生産量は5000立方㍍に届かなかったが、17年度は2万立方㍍以上を実現したい」(中島会長)。発足時に3社だった会員数は現在329社に増え、特に昨年末から今年にかけてゼネコンの加盟が目立つことから、いよいよCLT建築が本格化するとの認識が浸透したのではないかという見解も示された。
CLTで地方創生を実現する首長連合の参加首長からも、「17年度に道の駅の再整備でCLT物件を建てる」(群馬県下仁田町)、「温泉施設の改修工事でCLTを採用」(高知県北川村)、「17年度にレジャー用の施設をCLTで作ることを検討」(同大豊町)、「体育館建設にCLTを採用できないか検討したが、コストの問題で断念した。約2年後に木造物件を建てる計画があるので、その時はCLTを使いたい」(福島県古殿町)などの報告が続いた。
今後の活動方針として、デベロッパーにCLTを使うように働き掛けていくことや、駅・空港のベンチ、商業施設のいす、机、間仕切り、店舗の棚などにCLTの採用を呼び掛けていくことが確認されたほか、古屋圭司会長代行が「全国に5万件ある郵便局の建て直しにCLTを採用してもらえないか、総務省と連携するべきではないか」と提案した。
2017年3月25日(土)日刊木材新聞より
◆CLTで需要増を
高層ビルや老健施設に かごしまCLTシンポ
鹿児島県はさきごろ、鹿児島市内で「かごしまCLTシンポジウム」を開いた。同県は新需要となり得る部材として、今後CLTを普及させていきたい考えだ。県内の山佐木材(肝属郡)も、CLTでJAS認定を取得している。普及への取り組みとして、これまで木造の建築士を集めた研修会などを行っており、今回のシンポジウムもその一環となる。
当日は既に木造を扱っている、また木造に興味を持つ設計士や工務店などを中心に約150人が参加した。佐々木幸久山佐木材社長と加治木百年センチュリーハウス社長、建築家の武松幸治E.P.A環境変換装置建築研究所代表、渋沢龍也森林総合研究所複合材料研究領域複合化研究室長が、CLTの可能性などをテーマにパネルディスカッションを行った。有馬孝禮東京大学名誉教授がコーディネーターを務めた。
佐々木社長は今年、「同社のCLT工場を整備し、年間1万立方㍍まで生産量を拡大させる。超高層ビルを含む鉄骨ビルの床や耐震壁などの一部にCLTを活用することで、同材に馴染みのない施主にも提案できる」と話した。
センチュリーハウスは木造の一般住宅を中心に手掛けており、県内初となるCLTパネル工法での賃貸集合住宅を姶良市に建設中だ。加治木社長は鹿児島県の将来的な人口減や、それに伴う同社の仕事量減少が予想されるなかで、CLTを新規事業として伸ばしていければ良いと説明した。また、子育て世帯の住宅や老健施設などの需要が増えていくのではないかとの見通しを示した。「今後、CLTの建築コストがRCやS造並みに抑えられていくことを期待している」(加治木社長)と語った。
武松氏は基調講演で、自ら手掛けた国産材CLTを活用した非住宅物件などを紹介した。有馬名誉教授は「森林資源活用の意義と必要性」という題で講演した。
2017年3月26日(日)
◆日本森林学会市民公開シンポジウム 鹿児島で開催!
「木質バイオマス利用の現状と将来」
・日時:3月26日(日)13:30~16:30
・場所:鹿児島県民交流センター県民ホール
・事前申し込み不要
・受講料無料
・基調講演:沖 修司氏(林野庁次長)「木材利用をめぐる新たな潮流」
・話題提供:近藤 博氏(中越パルプ木材㈱原燃料部長)、
木口 実氏(森林総合研究所 研究ディレクター)
佐々木 幸久(山佐木材㈱代表取締役)
※詳細は添付PDFをご参照ください。
お問い合わせ先:TEL 099-285-8571、FAX 099-285-8571 鹿児島大学農学部公開シンポジウム担当
2017年3月4日(土)
◆鹿児島県主催「かごしまCLTシンポジウム」開催!
・日時:3月4日(土)13:30~16:30
・場所:マリンパレスかごしま アクセス
・定員:150名(先着順)、受講料無料
・基調講演①:有馬孝禮氏(東京大学名誉教授)
・基調講演②:武松幸治氏(建築家、E.P.A環境変換装置建築研究所代表)
・パネルディスカッション「木造建築の魅力とCLTの可能性を語る」
当社からは佐々木社長がパネリストとして参加いたします。
※参加申込については、添付PDFにて下記に直接お申し込みください。
申込・お問い合わせ先:TEL 099-224-4543 FAX 099-226-3963 鹿児島県木造住宅推進協議会


〒893-1206
鹿児島県肝属郡肝付町前田2090
TEL:0994-31-4141
FAX:0994-31-4142