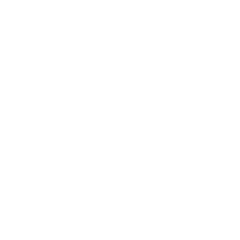News
2018/1~
2018年11月3日(土)日刊木材新聞
2例目物件の建築進む
仙台の10階建てマンション 超高層ビルに木材を使用する研究会
超高層ビルに木材を使用する研究会(稲田達夫会長、法人会員25と個人46)はさきごろ、福岡市内で通常総会及び記念シンポジウムを開催した。会は中・高層木質混合構造建築への木材の活用を促進させることを目的に発足。佐賀市内で2時間耐火の杉CLT床を実物件として初採用した松尾建設本店が竣工している。そのほか現在、建設中の物件もあり、中・高層建築での同床活用は着実に前進している。
現状で4~10階の床に杉CLT材を使用した、鉄骨造と木造による混構造10階建て賃貸マンションの建設が仙台市泉区高森2丁目で進められている。三菱地所と三菱地所設計、竹中工務店、山佐木材の4社で取得したCLT床2時間耐火構造の技術を適用したものだ。
また高層建築ではないが、沖縄県の下地島空港(宮古島市)旅客ターミナルの整備も行われている。約1500立方㍍のCLTを屋根構造と壁の一部に使用する。同材は山佐木材が供給した。
会では昨年度、松尾建設の建築現場見学会などを計7回実施した。CLT材増産に向け同加工機やモルダーラインなどの設備投資を行った山佐木材・下住工場の見学などを行った。
シンポジウムの基調講演では京都大学大学院建築学専攻助教授の小見山陽介氏が、ロンドンに建てられた7階建てCLT造集合住宅など、中・高層物件への木材活用における動向を報告した。
三菱地所住宅業務企画部CLTユニット主事の海老澤渉氏は、同社が手掛ける仙台市泉区高森2丁目物件について説明した。
鹿児島県主催「かごしまCLTシンポジウム」開催されます
■日時:10月20日(土)13:30~16:30
■場所:かごしま県民交流センター中ホール(西棟2階)
■内容
(1)13:30~13:35 あいさつ(鹿児島県環境林務部)
(2)13:35~14:20 基調講演① CLT工法建築物のコスト比較
(一社)岡山県建築士事務所協会常務理事 武田賢治氏
(3)14:20~15:05 基調講演② 鉄骨構造建物のCLT床利用の可能性
超高層ビルに木材を使用する研究会会長 稲田達夫氏
(4)15:15~16:30 パネルディスカッション「CLTの可能性を語る」
■参加費:無料
■定員:150名
■申込:下記ご案内をダウンロードいただき、参加申込書ご記入の上、事務局へFAXしてください
※申込締切 10月15日(月)
2018年9月24日(月)南日本新聞
CLT工法へ熱視線 木造中高層建築に導入拡大
山林の適正活用期待 コスト減や周知課題
耐震性や耐火性に優れた建材「直交集成板(CLT)」で可能となった木造の中高層施設の建設が、鹿児島県内でも広がっている。県産材の新たな需要開拓を通し、森林資源が豊富な県内経済の活性化や山林の適切な管理につなげたいとの関係者の期待は大きい。断熱性や施工のしやすさといった特性もあるだけに、より一層の普及には素材自体のコスト削減が課題になってくる。 (右田雄二)
「建築現場での労働力不足が進む中、工期を短縮できるメリットは大きい」。センチュリーハウス(鹿児島市)の加治木百年社長(50)は力を込める。今年1月、CLTパネル工法を使い、県内初の木造3階建て賃貸アパート(12世帯)を姶良市に建設した。
CLTは強度を強くするため木材を直交するようにして貼り合わせた面状の建材。柱を使わなくても、パネルを組み合わせるようにして建設でき、作業が比較的容易なのが特長だ。
今回のアパートは中高層施設で主流の鉄骨や鉄筋コンクリートと比べ、2カ月ほど工期を短縮することができた。骨組みに使う素材費は鉄筋コンクリートと同程度だったが、人件費を含めた総費用は1割ほど安くなったという。
七呂建設(鹿児島市)も、CLTで新社屋2棟を建設中だ。七呂恵介社長(41)は「鉄筋コンクリートよりも建築物を軽量化でき、耐震性も確保できる。コスト削減が進めば需要はさらに増える」とみている。
CLTは断熱性に優れ、空調の省エネ効果が見込めるほか、鉄骨や鉄筋に比べ、製造時に必要なエネルギーが少ないため、環境に優しい利点もある。センチュリーハウスと七呂建設は、県内産木材の新たな需要開拓を目的にした県の補助金を活用した。
県によると、県内でCLTを使った施設は建設予定も含めて現在12となっている。
県の2017年3月の人工面積は27万9千㌶で九州2位。多くが利用可能時期を迎えている。一方、人口減の中、木造を含む一戸建て住宅の建設数が今後大幅に伸びる可能性は低い。森林総合研究所九州支所(熊本市)の森林資源管理研究グループ、横田康裕主任研究員(48)は、「地域にある木材を利用していくことが、地域経済の持続的発展や、土砂災害防止などの山の多面的機能の維持にもつながる」と指摘する。
日本CLT協会(東京)理事で、CLTを製造する山佐木材(肝付町)の佐々木幸久社長(72)は「需要が増えれば素材コストは下げられる。普及に向けCLTを使った設計方法などを紹介していきたい」と説明する。
宮崎県は耐震性強化を掲げ、現在整備を進める10階建て防災拠点庁舎の4~9階の壁に地元産材によるCLTを利用する。鹿児島県内関係者からは「鹿児島にもCLTの魅力を紹介できるランドマークとなる施設が欲しい」との声が上がる。
県かごしま材振興課の小林孝幸課長は「CLTは林業活性化の切り札。各市町村にCLTの利用を呼び掛けるなど、需要拡大に力を入れていきたい」と話している。
2018年9月20日(木)日刊木材新聞
年販売量引上がる
下地島空港への供給で 山佐木材
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は、10年以上前から防腐・防蟻処理木材を展開している。同社が出資する協同組合きもつき木材高次加工センターの加圧注入釜などを活用する。製材や集成材、CLTの処理木材の販売量は直近で年間5000立方㍍。例年の平均販売量を上回った。
年間の平均販売量は3000~4000立方㍍で推移する。同社は沖縄県下地島空港(宮古島市)の旅客ターミナル施設整備で使用されるCLTを供給する。同施設に使用するCLT材などをホウ酸系処理剤ボラケアを使用して処理、供給したことで販売量も増えた。
同社の販売する処理木材は、きもつき木材高次加工センターの加圧注入釜でティンボアを注入するケースがあり、同センターの注入釜は1基体制だ。集成材やCLTなど、注入釜に入らない製品はボラケアで処理される。
供給地域には沖縄や離島なども含まれる。白アリの被害が懸念されるなど条件の厳しい場所で使用される場合は、家や施設1棟分などの処理を提案している。
2018年9月18日(火)メルマガ臨時号
超高層ビルに木材を使用する研究会:第6回総会および総会記念シンポジウム開催いたします
■日時:10月12日(金)12:30~会員受付開始、13:45~一般受付開始
■場所:TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター701会議室
■内容
(1)13:15~13:45 総会
(2)14:00~14:10 シンポジウム開会、主催者挨拶、来賓挨拶
(3)14:10~15:00 基調講演
<基調講演>「世界の動向 環境・木造・森林」
京都大学大学院建築学専攻助教 小見山 陽介氏
(4)15:10~17:30 パネルディスカッション
「大規模ビル型建物への木材の活用促進に向けての道筋-建設コスト削減と需要拡大-」
(5)18:00~20:00 意見交換会 博多炉端「野が海」
■参加費:無料(※意見交換会は会費5,000円を予定)
■定員:80名 ※会員優先、会員外は先着順
■申込:下記ご案内をダウンロードいただき、参加申込書ご記入の上、事務局へFAXしてください
※申込締切 10月3日(水) 受付を締め切りました
2018年9月13日(木)日刊木材新聞
CLT使用高層建築 工事進む 三菱地所
湿式工法で2時間耐火CLT床の工期短縮
三菱地所(東京都、吉田淳一社長)が仙台市の泉パークタウン内で建設中の、日本初のCLTを利用した高層建築「泉区高森2丁目プロジェクト」(仮称)の工事が進んでいる。木造+S造のハイブリッド構造による10階建て賃貸マンションで、延べ床面積の約3割にCLTを使った湿式工法による2時間耐火床を採用。耐震壁の一部にもCLTを使った。
マンション居室に現しになる2本の柱に「燃エンウッド」を用い、2~6階は荷重支持部カラ松・燃えしろ層杉による2時間耐火、7~10階は荷重支持部・燃えしろ層杉による1時間耐火認定品と使い分けた。同社では「内装で木材を使った居室とそれ以外の居室での経済的な評価も長期間にわたり調査していきたい」と話している。
このプロジェクトは三菱地所の若手4人が、工事費高騰、職人不足による工期長期化など建設業界の課題の解決に向けてR&Dのプロジェクトとして提案し、住宅業務企画部兼新事業創造部にCLTユニットが誕生した。CLTを使ったプロジェクトでは下地島の空港施設と泉区高森2丁目プロジェクトが同時進行している。
CLTを使った2時間耐火構造の床(4~10階)では、上面はALC36㍉+強化石膏ボード15㍉2枚張りの乾式工法で大臣認定を取得しているが、「施工に掛かる人工が十数人と多く、湿式工法にすることで40平方㍍くらいなら2~3人で施工でき、1フロア半日で施工できる」(施工を担当した竹中工務店)。床にはCLT210㍉、5層7プライMx60を使用し、SLプラスター60㍉、トップコンクリート80㍉を打設。下端は強化石膏ボード15㍉3枚、ケイ酸カルシウム板15㍉を施工する組み合わせで、三菱地所、三菱地所設計、竹中工務店、山佐木材で2時間耐火構造の認定も取得した。
H鋼による梁の天端にCLTの端部を30㍉乗せ、鉄骨梁とCLTは直径70㍉のスタッドで固定。床CLTには溝加工して固定用鉄筋を入れたうえでコンクリートを打設する。
1~5階の耐震壁にはCLT150㍉、5層5プライを使用。鉄骨梁に固定用鉄骨ブロックとせん断プレート(ストローグ)+ドリフトピン、下端はCLTをコッター加工し、コンクリートを凹部に流し込み固定している。
CLT(山佐木材)は199.8立方㍍、燃エンウッド(斎藤木材工業)は18.5立方㍍を使用した。
敷地面積3550.78平方㍍、延べ床面積3620平方㍍、地上10階建て、建物高さ33.695㍍、設計・施工は竹中工務店。
工期は2018年3月~19年2月を予定している。
2018年9月6日(木)日刊木材新聞
丸太打設工法や木橋の研究報告 土木学会
佐々木山佐木材社長が特別講演
土木学会木材工学委員会(吉田雅穂委員長)はさきごろ、東京・四ッ谷の土木会館講堂で「第17回木材利用研究発表会」を開いた。特別講演を行った佐々木幸久山佐木材社長は、国産材は森林所有者が分かり森林経営を行う有効林率と、再造林率を掛け合わせて、持続的な利用が可能となる、生長量の半分くらいに年間伐採量に規制を設けるべきとの持論を述べた。
7日の研究発表会では、丸太打設による地盤補強や軟弱地盤対策に関する研究発表と木橋の健全度調査などが行われた。三村佳織氏(兼松サステック)は、軟弱地盤に打設した丸太のテーパー効果について、熊本での打設試験の結果から同効果が認められたことなどを報告した。
本田秀行金沢工業大学教授は、過去に建設された木橋の健全度を定量的に評価する手法の構築に取り組み、減点法による各測定法を統合して普及度、健全度評価を試みた。
特別講演で佐々木社長は山佐木材のこれまでの事業の取り組みを振り返り、1990年ごろまでは木造規制時代、それ以降2016年までを木造緩和の時代、そして現在を木造推奨の時代と区分。時代に応じて、製材、大断面集成材、CLTなど新たな事業に取り組んできたなかで大隅半島の森林状況を見ると、森林が過伐になっている。それは民有林の所有者が分かり、森林施業を行える有効林が少なく、伐採して再造林できる森林を対象に林業は考えていくべきで、生長量に見合った伐採量に伐採届が出された時に、その年の伐採量に応じて規制を設けるような時代が来ていると話した。
そのうえで、自社では森林を経営資源としてとらえ、過疎地域の雇用の受け皿となるように都市部へCLTなど付加価値のある木材を供給していきたいと述べた。
平成30年6月1日林野庁公表
「森林・林業白書」に山佐木材の取組が紹介されました
2018年6月21日(木)
Aパネ工法(木造在来軸組+CLT) 説明会が開催されます
当社が製造している厚さ36mmのCLT(Aパネ)を木造在来軸組の構造用面材として利用した「Aパネ工法」の説明会が福岡で開催されます。
※AパネはJAS構造材利用拡大事業の対象であるCLTのJAS材であり、要件を満たせば、CLT使用量m3あたり150,000円の助成を受けることが出来ます。(JAS構造材利用拡大事業について→リンク)
・日時:2018年7月27日(金)13:30~16:30
・場所:キャナルシティビル4階 TOTO会議室(定員80名)
(福岡市博多区住吉1-2-25)
・参加費:無料
・申込:添付PDFに必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・締切:2018年7月23日(月)※定員になり次第終了
・お問い合わせ先:Aパネ工法普及協議会事務局
https://www.apane-clt.com/ TEL 058-370-1884/FAX 058-271-5630
2018年5月26日(土)日刊木材新聞
佐々木理事長が再選
中大規模担い手育成に着手 日集協総会
日本集成材工業協同組合(佐々木幸久理事長)の第47回通常総会が18日、東京都内で開かれ、任期満了に伴う役員改選で佐々木理事長が再選された。今期は林野庁の補助事業の採択を受けて中大規模木造工事の担い手の確保・育成に向けた資格・研修制度を検討。森林総研と共同で国際競争力を強化するための構造用集成材等の国産木材製品の低コスト化などにも取り組む。なお、専務理事の片岡辰幸氏が退任し、清水邦夫氏が新たに就任した。
佐々木理事長は「日集協の会員は業種、業態が多種多様で、同じ集成材でも広葉樹、針葉樹、輸入材、国産材と幅広く、多様な会員のニーズ、マーケットのニーズにどう応えるかは難しい課題。及第点とはいかないが、副理事長や事務局、関係者の助けをいただき、2年の任期を何とか全うできた。今後もご指導をよろしくお願いしたい」とあいさつした。
昨年度の事業報告では、展示会への出展や文化財の復元・修復への集成材利用の促進、大断面集成材の規格化、中大規模木造建築物の担い手の確保及び専門資格制度の創設に向けた検討、国への要望活動などを報告した。
このうち、大断面の規格化については、一般流通材と競合しない3、4階建ての事務所ビルや、中断面では難しい大スパン物件などを対象にサイズを絞り込み、4月から平均単価の公表を始めた。中大規模木造工事の担い手の確保・育成に向けた資格・研修制度の検討については、林野庁補助事業の採択を受けて今年度から具体的な仕組み作りに着手することが決まった。
来賓からは、前田武志日集協顧問、猪島康浩林野庁木材産業課長、武井利行国交省木造住宅振興室長、前田直登日本林業協会会長、古久保英嗣日本住宅・木材技術センター理事長が祝辞を述べた。
2018年5月22日(火)日刊木材新聞
非住宅での製材の可能性探る
品質表示の改善、設計士との協力重要 国産材製材協会
国産材製材協会(佐川広興会長)は、このほど東京都内で開いた第13回通常総会に併せ、「製材品でつくる中大規模建築の可能性」をテーマとした講演会を開き、約80人が参加した。
講演したアトリエフルカワ一級建築士事務所の古川泰司代表は、「設計士と製材の供給側が歩み寄り、お互い協力し合える仲間作りができないと、中・大規模木造が一過性の流行で終わってしまう可能性がある。どこにどういう木がどれくらいあって、どこの工場がどういう木を挽けるのかが分からず戸惑うことも多いので、そういうことをコーディネートする存在の重要性が増していると感じている」と述べた。
古川代表は、通常手掛ける木造住宅の設計に加え、埼玉で2016年3月に完成したわらしべの里共同保育所の設計を手掛けた経験から、「品質が担保された木材を使いたいと思っても、木材の品質表記はJAS材でも目視等級と機械等級があり、無等級材でも機械グレーディングや目視による1等、特1等など様々で、設計士は混乱している」と述べ、分かりやすく統一された品質表記の重要性を指摘した。
一方、設計士側の課題も挙げ「必要な材はプレカット工場に頼めばそろうという考え方も聞くが、適材適所で素材を生かすのが設計士の仕事。例えば保育所の設計では、構造設計者からヤング率E-90以上でそろえてほしいと言われて難しいと思ったが、再度計算してもらったところ、約半分は70以上で良いことになった。こうした作業を丁寧にやれば、製材の可能性はもっと広がると思う」と述べ、お互いの歩み寄りが重要と指摘した。
国が整備する公共建築物を管轄する国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課の中山義章木材利用推進室長は、「木造化の意識は浸透しているが、コストは課題。例えば自転車置き場や倉庫など簡易な建築物は、木造の標準仕様のようなものがあるとコストも抑えられるのではないか。公共建築物は木造から離れていたので情報が少ない面も感じている。各地方の整備局に材料や技術などの情報を積極的に持ち込んで発信してほしい」と述べた。
佐々木幸久山佐木材社長は自社で手掛けているCLT建築や鉄筋補強集成材SAMURAIを紹介し、自身の経験を基に「製材という事業は利益率が低く。製材だけでなく、素材生産を手掛けたり、建築物の設計や建て方の技術や資格を身に着けることが今後の製材工場の生き方ではないか」と提案した。
意見交換の場では非住宅での製材の可能性に質問が相次ぎ、古川代表は「1000平方㍍を超えてくるとムク製材では難しいと思う。調達方法にも違いがあると感じる。保育所の入札時にゼネコンから、集成材なら商社から調達できるので、集成材にしてほしいという意見があった」と自らの経験から意見を述べた。
中山室長は「公共建築物は天井が高い大空間を必要とすることが多いが、製材は長さが4㍍を越えると価格が高くなる。公共調達としては様々な材のコストが下がり、色々使えることが重要」と話した。
2018年5月28日(月)
MBCテレビ「ふるさとかごしま」に山佐木材のCLT
山佐木材のCLT部が、テレビに少し出ました。
- 番組名:ふるさとかごしま
- 放送予定:5月26日(土)11:15~11:30
- (再放送 5月29日(火)深夜 01:45~ 2:00)
- 放送局:MBC南日本放送
- タイトル:拡げよう!かごしま材
※MBCホームページやYouTubeで視聴可能となっています
https://blogs.mbc.co.jp/furukago/
動画はこちら(6分50秒あたりから山佐木材が出ています)
2018年5月24日(木)
MBCテレビ「ふるさとかごしま」に山佐木材のCLT
山佐木材のCLT部が、テレビに少し出ます。
- 番組名:ふるさとかごしま
- 放送予定:5月26日(土)11:15~11:30
- (再放送 5月29日(火)深夜 01:45~ 2:00)
- 放送局:MBC南日本放送
- タイトル:拡げよう!かごしま材
※テレビ放送は鹿児島のみですが、MBCホームページで5月27日から1年間視聴可能となるそうです
https://blogs.mbc.co.jp/furukago/
予告動画がアップされていました
2018年4月24日(火)日刊木材新聞
構造計算含め技術提案
CLT生産能力も引き上げ 山佐木材
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)の構造用集成材の月間生産量は300立方㍍。構造用集成材事業では、中大規模木造物件向けの構造材生産と構造設計、加工建て方まで含めた受注生産が主だ。同社は製材、CLT製造も手掛ける。今後も、構造計算を含めた技術的提案のできるメーカーとしての営業展開を進める。同時に、防・耐火、遮音などの試験研究や開発にも取り組む考えだ。
杉構造用集成材の材長方向に鉄筋を挿入し、性能を高めた集成材「SAMURAI」の開発・普及支援も行う。JAS認定は大・中・小断面、杉と米松の異樹種構造用集成材、CLTは杉、杉と桧の異樹種CLTで取得している。
最近の主な供給実績は、構造用集成材は鹿児島県種苗生産施設ブリ種苗生産棟の新築工事に92立方㍍。由布市(大分県)インフォメーションセンター新築工事には87立方㍍を供給し、うち湾曲材が71立方㍍だった。
CLTは森林総合研究所九州支所(熊本市)の共同特殊実験棟の建て替え工事に530立方㍍を供給した。下地島空港(沖縄県宮古島市)ターミナルビルの新築工事に1560立方㍍。同物件は空港ターミナルとして全国初のCLT採用施設となる。
昨年は同社下住工場内にCLT工場棟とモルダーライン棟が完成し、11月中旬以降に本稼働を始めた。CLT工場棟に同加工機(ユニチーム)、モルダーライン棟にモルダーやグレーディングマシンなどを導入した。
同社の従来のCLT生産能力は年間4000立方㍍。繁忙期にCLTパネル生産が追い付かないことがあり、今後も長期的には同材の需要増が見込めることから設備を増強した。3年後に同能力1万立法㍍まで引き上げる事業計画となっている。
2018年4月24日(火)日刊木材新聞
大断面集成材を規格化、平均単価公表
標準化で競争力強化へ 日本集成材工業協同組合
日本集成材工業協同組合(佐々木幸久理事長)は、大断面集成材の部材寸法、接合部仕様の標準化を目的に規格化サイズを設定し、平均単価の公表を始めた。一般流通材と競合しない3、4階ての事務所ビルや中断面では難しい大スパン物件などを対象にサイズを絞り込んだ。普及品としての価格競争力、納期対応力を高めることで積極的な活用を促し、設計法や技術開発の進展につなげる。
大断面集成材規格化検討会による5回の討議で意見集約した。
規格化したサイズと単価(3月時点)は別表のとおり。樹種は杉(E65)とカラ松(E95)の2種類。部材の長さ、高さは3、4階建ての事務所ビルや中断面では難しい大スパン物件を想定、幅は燃えしろ設計やLSB(ラグスクリューボルト)などの接合具の使用を想定した。
価格は日集協が大断面集成材を生産する会員企業15社から聞き取り、平均単価(工場オントラ)を公表する。流通が定まった段階で調査価格として、建設物価版、積算資料などへの掲載を働き掛ける方針だ。
個別設計による受注生産で供給される大断面集成材は、部材寸法、接合部仕様も様々で、設計をしてからでないと見積もりを出せないため、予算を立てにくく、RC造やS造に対して価格競争力を発揮しにくい現実があった。部材を標準化すれば接合部や工法の標準化も進み、価格競争力、納期対応力の向上が見込めると判断した。
今後は規格部材やエキストラ部材の追加とともに、中層大規模木造研究会などの協力を得ながら、汎用性のある接合部仕様なども検討していく。
規格化に参加したメーカーは次の15社。
遠野グルーラム、秋田グルーラム、藤寿産業、小池住建、栃木県集成材協業組合、志田材木店、ラミネート・ラボ、中東、齋藤木材工業、セブン工業、片桐銘木工業、トリスミ集成材、銘建工業、中国木材、山佐木材。
2018年4月24日(火)日刊木材新聞
許可業種化に向け活動強化
資格創設、担い手育成へ 日集協
日本集成材工業協同組合(佐々木幸久理事長)は大断面集成材の普及拡大に向けた活動を活発化させている。昨年は部材寸法や接合部仕様を標準化するための規格化サイズをまとめたほか、木材、住宅、建築、設計など10団体で構成する木質構造工事業ワーキンググループ(WG)で、建設業の新たな許可業種としての「木質構造工事業」の創設や、中大規模木造建築工事の担い手の確保・育成に向けた資格・研修制度の構築を国に求める活動もした。規格化サイズは平均単価とともにこのほど公表を開始。WGの活動も今年度はさらに加速させる方針だ。
規格化したのは杉(E65)とカラ松(E95)の2種類。3、4階建ての事務所ビルや中断面では難しい大スパン物件を想定してサイズを集約した。
個別設計による受注生産で供給される大断面集成材は、部材寸法、接合部仕様も様々で、設計をしてからでないと見積もりを出せず、予算を立てにくいうえ、RC造やS造に対して価格競争力を発揮しにくい。部材を標準化すれば接合部や工法の標準化も進み、価格競争力、納期対応力の向上が見込めると判断した。
一方、WGでは建設業における木質構造工事業の創設を国交省に要望したほか、「鋼構造建築工事業」をモデルに、現場施工管理(管理者)、工場加工・現場架設(技能者)の2つの資格を設けたうえで、施工能力を見える化(格付け)できる仕組みの創設を求めた。建設会社が中大規模木造を公共工事で受注しても、どこの設計事務所、建築会社に下請けを頼めば良いか分からないケースが多い。だが、許可業種になれば発注先が明確になり、業種としてのステータスも見込めると見ている。
まずは資格、研修制度の創設に向けた取り組みを進める考えで、今年度の林野庁の補助事業に申請している。WGの委員長を兼ねる佐々木理事長は「RCと木質構造、住宅と非住宅は設計も技術も異なり、木質構造の非住宅にふさわしい資格がない。WGの委員中心に応募し、有識者にもアドバイザーで入っていただきながら、内実の伴った資格を作り、担い手育成に取り組みたい」と話している。
2018年4月23日(月)南日本新聞
農漁村に生きる
林業改革へ知恵絞る 鹿屋市 新永 智士さん(36)
集成材メーカーとして全国から注目を集める山佐木材(肝付町)に4月に入社したばかり。総務経理部の次長という重職に就き、経営計画の策定などに知恵を絞る。
鹿児島市出身で、高校卒業後に県外に出て以来、古里で仕事するのは初めてだ。「林業の現場を変え、若い人が働きたいと思える職種にしていきたい。地元の活性化にも貢献できれば」と意気込む。
経歴は多彩だ。京都大学から大学院に進み、丸太の生産性向上について研究を続けた。修了後、コンサルティング会社で林業を含む約40社の業務改善や、林業会社で経営に携わった。経営学修士(MBA)も取得し、2017年12月からは鹿児島大学客員准教授として林業関係者に経営指導する役割も担う。
佐々木幸久社長(71)と学生時代から知り合いで、2年ほど前に誘われたのが転職のきっかけ。「林業を変えたい」との社長の熱意に共感したという。
「林業の面白さは、過去と未来のつながりを感じられるところ。現在の木は過去に誰かが植えてくれた。今、山を守っていかないと100年後には切る木がなくなる可能性もある」と熱心に話す。
国内の林業は、人工林伐採後に木を植えない再造林放棄や労働力不足をはじめ課題が山積している。「販路拡大や経営の効率化が必要。簡単には解決できないが、だからこそ、やりがいがある」(右田雄二)

2018年4月5日(木)日刊木材新聞
CLTの野外施設完成 新潟県
外部も現し仕上げ
新潟県胎内市でCLT工法による県立青少年教育施設(仮称)野外活動支援棟が完成した。屋内外ともにCLT仕上げにして、ラミナは越後杉を活用した。このほど、設計事務所、工務店等を対象にした現地研修会を開いた。
建物概要は、木造CLT工法2階建て、延べ床面積377平方㍍。2階床・天井に厚さ150㍉(5層5プライ)、壁に同210㍉(7層7プライ)のCLTを125立方㍍使用した。
最大サイズは幅1874×長さ3999×厚さ150㍉、重さ394㌔。屋内外とも現しとなっており、接着剤性能は環境A(レゾルシノール・フェノール樹脂)。CLT製造は山佐木材、加工は志田材木店、設計は石動建築設計事務所、施工は小野組が担当した。
当日は研修会も開かれ、渡邉須美樹木構堂社長が「CLT建物の魅力について」のテーマで講演したほか、近藤勇二石動建築設計事務所設計部長が建物の概要について説明した。
同県は、2017年度に5カ所でCLT工法による施設整備を行った。18年度はその見学会などを通じて、新たに同工法に対応できる設計士の養成を支援していく。
2018年3月30日(金)日刊木材新聞
CLTと鉄骨の混構造事務所竣工 JR九州・熊本支社
勾配屋根で7.2㍍スパン実現
JR九州(青柳俊彦社長)はJR熊本駅(熊本市)の新幹線及び在来線高架下に移転する熊本支社の新事務所を、S造とCLT造の混構造1階建てで整備した。事務所棟の一部、また乗務員などが利用する乗泊棟が熊本県産を含む南九州産杉を使用したCLT造となる。事務所棟の会議室などは勾配屋根を採用したことで7.2㍍のスパンを飛ばし、高架下でありながら大空間を実現した。燃えしろ設計の準耐火構造で、屋根と壁に現しでCLTパネルを使用する。26日から新事務所での業務を開始した。
CLT使用量は製品ベースで330立方㍍。熊本県産杉が12%で残りが鹿児島県産となる。同パネルは銘建工業が事務所棟に、山佐木材が乗泊棟に供給した。一番大きいパネルはエントランス(事務所棟)の壁で長さ5000×幅2000×厚み210㍉。
7.2㍍スパンを実現する事務所棟の勾配屋根は、厚み150㍉のCLTパネルを地上で組み立てた後、揚重で取り付けた。安全面が確保でき、工期短縮にもつながった。JR九州の担当者は「CLT造で7.2㍍のスパンを飛ばしたのは国内初ではないか」と話す。
そのほか同棟では高架柱を囲むように効率的にCLT耐力壁が配置された。住友林業がCLT構造の設計、同部分の木躯体工事を担当した。
CLT造の事務所棟が1時間準耐火で、同造の乗泊棟が45分準耐火建築物となる。S造の事務所棟一部と会議室棟も耐火構造となる。
移転は熊本市が実施する熊本駅白川口駅前広場の整備事業に伴うもの。環境省の「木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業」の補助を活用した。木造部分とS造部分、それぞれの断熱性能の比較を今後3年間行っていく。建設費は全体で役11億円で、工期は昨年9月から今年3月まで。
新事務所の延べ床面積は3109.01平方㍍で、そのうちCLT構造部は1256.33平方㍍。建築設計は安井建築設計事務所、構造設計は同事務所と住友林業、施工は九鉄工業が担当した。新事務所では、乗務員や支社員など約140人が働く。
JR九州は近年では、大分支社の内装木質化などに取り組んでいる。ただ構造躯体に木材を取り入れるのは熊本支社が初となる。現在、具体的な計画はないものの、今後も機会があれば地元の木材を使っていきたい考えだ。
2018年3月29日(木)日刊木材新聞
日本初、CLT床材利用の高層建築 三菱地所
仙台で10階建てマンション着工
三菱地所(東京都、吉田淳一社長)は26日、CLTを床材として使用した日本初の高層建築物「仙台市泉区高森2丁目プロジェクト」(仮称)を着工した。この物件は、三菱地所、三菱地所設計、竹中工務店、山佐木材の4社で取得したCLT床2時間耐火構造の技術を初めて適用した。鉄骨造と木造による混構造10階建ての賃貸マンションで、2019年2月下旬の竣工を予定している。
このビルは10階建て、延べ床面積3604.79平方㍍、総戸数39戸となる。CLT床の2時間耐火認定は下面から強化石膏ボード15㍉厚×4枚+CLT150㍉、トップコンクリート80㍉、SLプラスター60㍉の順。CLT床を乾式だけで2時間耐火とする場合、石膏ボードの施工手間が掛かることから、CLT上部に衝撃音の低減と抑制機能があるトップコンクリートとSLプラスターの湿式工法を併用することで施工性を向上させる狙いがある。
CLT利用に当たり、林野庁、国土交通省の補助金制度を活用し、中高層建築物の木造化に関するリーディングプロジェクトとして工事費の削減、工期の短縮、国内の森林資源循環への貢献に寄与することを目指している。
床に215立方㍍、壁に17立方㍍のCLTを構造材として使用、耐火集成材の燃エンウッドは17立方㍍使用する見込み。4~10階の床にはCLT150㍉を床面積の約30%に使用する。配管の必要な水周りなどはRCのスラブとの使い分け、乾式工事の範囲を広げてRC造に比べ3カ月工期を短縮。壁のCLTは1~5階の耐震壁の一部で使用を予定している。
2~10階の居室の柱には竹中工務店の2時間耐火仕様の燃エンウッドを使用し、マンションの中に現しで木材が見える構造柱とする。
三菱地所は、同社の不動産開発などの規模で生かせる木造建築の事業化を検討するため新事業創造部にCLTユニットを組織し、三菱地所だけでなく、三菱地所設計、三菱地所ホーム、三菱地所住宅加工センターの協力体制で取り組んでいる。
CLTを活用するために様々な検討を重ねた結果、中高層建物の床での使用に可能性があると考え、施工性を考慮した仕様での開発を進めCLT床2時間耐火認定を取得した。
このほか、沖縄県下地島空港施設でCLTを屋根構造に使用した旅客ターミナルのプロジェクトも進行している。
2018年3月26日(月)三菱地所プレスリリース資料より
~日本初、CLTを床材として利用した高層建築物~
「(仮称)泉区高森2丁目プロジェクト」着工
工期短縮・国内の森林資源循環への貢献を目指す
三菱地所株式会社は、仙台市泉区「泉パークタウン」内で進めている賃貸マンション「(仮称)泉区高森2丁目プロジェクト」の新築工事を本日3月26日に着工しました。竣工は2019年2月下旬を予定しています。
本プロジェクトは、CLTを床材として使用した日本初の高層建築物であり、10階建賃貸マンションとなります。また、三菱地所株式会社、株式会社三菱地所設計、株式会社竹中工務店、山佐木材株式会社の4社にて取得したCLT床2時間耐火構造の国土交通大臣認定技術を初めて適用した建物です。本プロジェクトの設計と今後の施工段階での実証により、2時間耐火構造技術を含めた防耐火技術・構造技術および施工方法において合理化手法の確立を目指します。
また本計画地は、周辺にホテルや商業施設、アウトレット等が集積する街の中心部に位置し、小高い丘陵地に建つことから視認性も高く、街の新たなシンボルとなることが期待されます。
↓続きは添付PDFをご参照ください。
2018年3月9日(金)日刊木材新聞より
防腐・防蟻など成果報告
日本CLT協会・林野庁委託事業
日本CLT協会(中島浩一郎会長)は5日、東京都内で2017・18年度実施の「CLT関連林野庁委託事業成果報告会」を開き、150人が参加した。CLTの防腐・防蟻処理基準についてのAQ品質性能評価基準案について日本住宅・木材技術センターが報告したほか、CLTの普及に向けた技術開発について報告された。
日本ツーバイフォー建築協会の佐藤昌義氏は、「CLTを活用したツーバイフォー工法の新展開」と題して話した。17年9月の告示改正で2×4工法の床版、屋根版にCLTが使用できるようになったことに言及。準耐火建築物の場合はCLTの燃えしろ設計でCLTを現しで使用できるようになり、2×4工法でも木材現しの使用が可能になった。また、設計実務者向けにCLT活用のガイドブック(A4判、カラー24ページ)を作成したことを紹介し、2×4工法でのCLT現し使用の参考事例などを示した。
山佐木材の小松賢司氏は、大判のCLT製造が可能なメーカーが限られているため、小判CLTをFJで接合して大判化することを目標にした研究を実施。CLT同士をFJ接合する際の最適嵌合圧の評価やラージフィンガー(50ミリ)、ノーマルフィンガー(24ミリ)での比較、幅はぎしたラミナをFJして積層したCLTの曲げ性能評価について報告した。CLTをFJで嵌合する際の最適嵌合圧は1N・平方ミリとし、FJされたCLTの面外、面内曲げ性能はいずれも告示562号の基準強度や等価断面法で得られるヤング係数を上回ったという。「工場だけでなく現場の嵌合方法も考えていく必要がある」と述べた。
2018年2月24日(土)日刊木材新聞より
GIR研究会が発足 SMB建材等6社で
訴求力高め市場活性化目指す
SMB建材(東京都、角柄明彦社長)木構造建築部(小川嘉男部長)を発起人に、グルード・イン・ロッド(鋼棒挿入接着接合、GIR)技術を持つ企業で構成されるGIR研究会が22日に発足した。同研究会は、GIR技術に関する意見交換や開発、木構造市場の動向や法令改正などの情報共有を図り、GIR技術の向上やGIRの市場開拓につなげていくことが狙い。昨年度から設立に向けた話し合いを重ね、22日から本格的な活動を開始することで合意した。
会員企業は、翠豊(岐阜県加茂郡、今井潔志社長)、スクリムテックジャパン(福岡県筑紫野市、河野泰之社長)、中東(石川県能美市、小坂勇治社長)、藤寿産業(福島県郡山市、蔭山寿一社長)、山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)、SMB建材木構造建築部の6社。
会長には小川SMB建材木構造建築部部長が就く。産官学連携を視野に、腰原幹雄東京大学生産技術研究所教授を顧問に迎えた。
GIRは、木質部材に開けた穴に鋼棒を挿入し、樹脂接着剤を充填することで部材同士を接合する方法。国内では、サミットHR工法やホームコネクター工法、RH構法などが展開されている。中大規模木造の構造躯体で用いられるだけでなく、戸建て住宅にまで幅広く利用されているほか、仕上げ内外装材にも活用されている。
一方で、企業がそれぞれに独自工法として展開しているのが現状で、GIRが汎用性のある工法になっていないという課題があった。
こうした課題を背景に、同研究会では、同会を通じて緩やかな企業連携を形成することで、GIRの啓蒙や普及、技術の共有を図ることなどでGIRの訴求力を高めていく。
当面、同研究会が対象とするGIRは、サミットHR工法、ホームコネクター工法、RH構法の3つとする。だが将来的には、他のGIR技術を基にする各社との連携も視野に入れていく。
同研究会では今後、広報学科会や技術分科会を設け、GIRのさらなる認知度の向上と、CLTへのGIRの適用、GIRの耐火構造への応用、靱性を持ったGIRの開発や施工性といった技術面の課題などに取り組んでいく。
さらに、標準接合基準の整備と共有を通じ、会員企業がそれぞれにGIR技術を一層磨いていく。
2018年2月16日(金)
CLT関連 林野庁委託事業成果報告会が開催されます
平成28・29年度のCLT関連林野庁委託事業17件について事業報告が行われます。当社も2件報告いたします。
・日 時:平成30年3月5日(月) 10:00~16:00
・会 場:全国町村議員会館 2階大会議室 (東京都千代田区一番町25)
・定 員:先着160名 要申込 入場無料 ※定員に達し次第、申込受付終了
・申込み:日本CLT協会のホームページよりお願いします。
2018年2月9日(金)
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター主催
CLTを活用した建築物等実証事業成果報告会
「CLTがもたらす新たな建築の世界」が開催されます
CLT実証事業を活用した21物件について、東京会場で10件、大阪会場で11件の事業報告が行われます。
■東京会場(成果報告会、住木センター講演会合同開催)
・日 時:平成30年3月8日(木) 11:00~16:30
・会 場:すまい・るホール (東京都文京区後楽1-4-10)
・定 員:先着300名 要申込 入場無料 ※定員に達し次第、申込受付終了
・申込み:住木センターホームページよりお願いします。

■大阪会場(成果報告会)
・日 時:平成30年3月12日(月) 13:00~17:20
・会 場:グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)会議室1202(大阪府大阪市北区中之島5-3-51)
・定 員:先着200名 要申込 入場無料
・申込み:住木センターホームページよりお願いします。

鹿児島県主催
木造建築関連技術者向けCLT技術講習会が開催されます
鹿児島県主催でCLTについての技術講習会が開催され、当社が講師をつとめます。
2017年2月に開催したものと基本的には同じ内容です。
・日時:2018年2月9日(金)10:30~15:40
・場所:鹿児島県社会福祉センター 7階大会議室(定員50名)
(鹿児島市鴨池新町1-7 TEL:099-251-3232)
※駐車場が満車の場合は鹿児島県庁駐車場をご利用ください
・参加費:無料
・内容:1.CLTの特徴と性能
2.CLTを活用した建築事例
3.国土交通省告示の解説
4.CLTを活用した建築設計手法 ※詳細は添付PDFをご参照ください
・申込:添付PDF裏面の申込用紙に必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・締切:2018年2月2日(金)※定員になり次第終了
・お問い合わせ先:鹿児島県木造住宅推進協議会事務局
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター企画部企画課
TEL 099-224-4543/FAX 099-226-3963
2018年1月11日(木)
Aパネ工法(木造在来軸組+CLT) 説明会が開催されます
当社が製造している厚さ36mmのCLT(Aパネ)を木造在来軸組の構造用面材として利用した「Aパネ工法」の説明会が東京で開催されます。施工事例紹介や設計・施工方法の解説などです。
・日時:2018年2月22日(木)13:30~16:30
・場所:一般社団法人 日本CLT協会(定員20名)
(東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋2F)
・参加費:無料
・申込:添付PDFに必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・締切:2018年2月15日(木)※定員になり次第終了
・お問い合わせ先:Aパネ工法普及協議会事務局
https://www.apane-clt.com/ TEL 058-370-1884/FAX 058-271-5630
2018年1月15日(月)
近畿木材利用建築促進フォーラム~CLT等様々な木材の利活用~が開催されます
林野庁・近畿中国森林管理局と国土交通省・近畿地方整備局が共に開催する初の取り組み。
山側から建築まで一体として情報提供されます。
・日時:2018年2月15日(木)14:00~17:30
・場所:近畿中国森林管理局 4階大会議室
(大阪市北区天満橋1丁目8番75号)
・参加費:無料
・申込:添付PDFに必要事項を記入しFAXで申し込んでください
・プレスリリース:
林野庁 近畿中国森林管理局
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/press/hanbai/180105.html
国土交通省 近畿地方整備局
http://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2017/20180105-2.html


〒893-1206
鹿児島県肝属郡肝付町前田2090
TEL:0994-31-4141
FAX:0994-31-4142