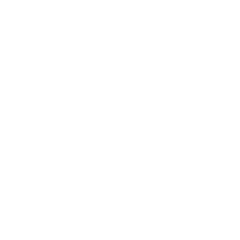━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★【稲田顧問】タツオが行く!(第14話)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「これまでのタツオが行く!」(リンク)
14.柔剛論争勃発
前節で述べたように、佐野利器等が制定に深く関わった市街地建築物法で、初めて地震荷重レベルに関する公式の規定が制定されたのは、1924年(大正13年)10月のことである。その特徴は、建物の高さは31m以下とし、耐震壁を設け建物の剛性を増すことにより耐震性を確保するという考え方で、震度法という極めて簡便な地震外力の計算法を採用したことであった。
この法律に対し、海軍建築局長の真島健三郎は、大きな違和感を持っていた。真島の主張は以下のようなものであった。
「濃尾地震以来ここまで育ててきた日本の耐震安全に対する考え方を、台無しにしかねない暴挙ではないか。そもそも、建物の高さが31m以下に規制してしまう必要がどこにあるのか。これでは、日本では米国のような摩天楼の建設はできなくなってしまう。本来、法で規定すべきは建物の安全性に対する方針・考え方である。例えば、この程度のレベルの荷重に対し、躯体に経年劣化を誘発するような、ひび割れは入ってはいけないとか。この程度の荷重に対しては、ひび割れが入るのはある程度やむを得ないとしても建物の倒壊は回避したいとか。ところが、高さを制限して壁を入れろという。それは耐震性を確保する一方法に過ぎない。そのようないわば作法、流儀の類を法にしたのでは、設計の多様性が損なわれてしまう。」
「今回は、RC構造の推進者である佐野先生達が、自分達の構法の普及に都合が良いように法案を決めてしまっているように思う。最近の彼らの論調を見ていると、例えば煉瓦造は面外方向に崩落するので、地震に弱いと書いている。しかし、丸の内の三菱一号館や三菱銀行本館は、煉瓦造であるにも関わらず無傷だった。要は、工夫をすればどんな構造でも成り立たないということはない。正しく構造設計がなされておれば、どんな構造でも安全にすることは可能である。確かに、煉瓦造はコストもかかるし、手間もかかる。しかし、コンクリートは経年劣化の問題があるが、煉瓦は基本的に劣化しない材料だ。永い目で見た時どちらが良い材料か判断は難しい。いずれにせよ、首都復興を意識するあまり、やや近視眼的になって、効率主義に陥っているように思う。」
真島は自分の意見をまとめ、日本建築学会の機関誌である「建築雑誌」に投稿したが、それはやがて建築界のみならず一般の人々も巻き込んだ全国民的議論へと発展する。遂に、柔剛論争の火ぶたがきって落とされたのである。
建築学会はこの問題に関する議論の決着を求めて、討論会を開催することにした。討論会には、真島と佐野が招弊された。討論会では、まず建設省から法制定に関する概略の説明があった後、構造設計が柔であるべきか剛であるべきかに関する討論に移った。まず発言が求められたのは、法制定に対する批判の急先鋒である真島であった。真島は以下のように自説を展開した。
「本来、建物構造が剛である方が地震に強いか、柔である方が強いかなどということは、比較すべき問題では無いと思います。一般的に言えば、建物が柔であろうと剛であろうと、正しく設計が行われていればいずれでも問題は無いわけでありまして、いずれが望ましいかというようなものではありません。ただ、建物の剛性と強度の関係だけで申し上げますと、剛性が上がりますと、建物の固有周期は短くなりますので、建物の応答加速度は増大します。従って、建物に働く力もそれに伴って大きくなるわけでありますから、それに耐えるためには、より高い強度が必要ということになります。一方、剛性が小さくなる、つまり柔になりますと、建物の固有周期は長くなりますので、建物の応答加速度は減少します。従って、建物に働く力は相対的に小さくなりますので、より低い強度で良いということになります。従って、これだけのことで申しますと、私は建物の剛性は柔であった方が良いと思っておるわけでありますが、ここでそのようなことを敢えて主張するつもりはありません。と申しますのは、建物の剛性は建物の形態によって変わるものだからであります。一般には高さの高い建物は柔であり、高さの低い建物は剛となります。間仕切りが多くなれば剛となり、少なくなれば柔となります。しかしこれらは、本来建物に要求される機能から決められるべきものでありまして、耐震性というようなもので決めるべきものではありません。
しかるに、この度の法の制定におきましては、建物に高さの制限を設けることにより柔な建物を実現する一つの有力な方法を選択する道を閉ざしてしまっております。米国には既に200mを超えるビルがいくつか建設されております。そしてこれは、勿論耐震性の問題から生じたものではなく、経済活動の中で自然発生的に生じたものであります。そしてこのような方法は明らかに耐震性の高い建物を設計する一つの解を提供するものと思われます。しかるに今後わが国ではこのような試みは、不可能となるわけでありまして、これは明らかに極めてゆゆしき事態と言わざるを得ません。このような事態を私は深く憂え、この度の反論を思い立った次第であります。どうか、諸兄におかれましては御賢察の上、この討論が実りのあるものとなりますよう、切にお願いする所存でございます。」
以上で真島の問題提起は終わった。代わって、佐野が演壇に立って、反論を行った。
「真島先生のご高説をご拝聴させて頂き、先生の耐震工学に対する高い見識と、熱意には感服致しました。しかし私と致しましては、何点か同意できない部分がございます。それにつきまして、まず意見を述べさせて頂きたいと思います。
まず第1に、先生は固有周期が長いほど相対的に固有周期が短い建物に比べ安全であるとの意見を述べられました。しかし、この度の地震で得られました教訓とは全く異なるものであります。高さが高い建物、例えば丸ビルでありますとか、日本郵船ビルでありますとか、比較的固有周期が長いと思われる建物は、実は大きな被害が出ております。一方、壁が設けられた、高さも低い、従って固有周期が相対的に短い建物におきましては、被害は比較的少ないということが言えます。例えば、日本興行銀行東京支店でありますとか、歌舞伎座でありますとかかが、それにあたります。いかに理論的には、真島先生の説が正しいと致しましても、このような事実を無視することはできないのではないでしょうか。
第2点と致しましては、実は今回施行致しました法制定の一つの利点は、震度法という建物の強度を確保するための簡便な方法を採用した所にあります。強度を増せば、剛性も上がるわけでありますが、その要求レベルを定めることにより、比較的容易に性能の検証を行えるのが、今回の法制定の利点であります。一方、柔構造が望ましいと主張される真島先生は、何か震度法に代わる方法を準備しておられるのでしょうか。いかに優れた理論であっても、実用的な方法が伴わなければ意味はないと考えますが、いかがでしょうか。」
佐野の反論に対して真島は応えて、
「まず第1のご質問の件でございますが、私は剛構造と柔構造で、どちらが優れているかということを申し上げたつもりはございません。ただ、要は正しく設計がなされておれば、剛でも柔でもかまわないのではないかと申しているのであります。ことさらに、正しく設計されている剛な建物と、設計上問題のあった柔な建物を比較して、柔の方が被害事例が多いから問題ではないかと申されるのは、筋違いではないかと思うわけであります。また、丸ビル、郵船ビルを引き合いに出されておられますが、そもそもこれらの建物が柔の代表と言えるのでありましょうか。たとえば、米国に建設されております200mを超えるような建物と同じ性質であるとするのは、無理があるように思われます。私はこれらの建物を柔の代表として議論することには同意致しかねます。
次に第2の点でありますが、柔な建物を評価する方法として、振動論がございます。本来地震による建物の挙動は全て振動現象でありまして、振動論で解決が図るのが正しい取組と言えます。震度法のように、地震を力として評価する方法は、本質的に間違ったアプローチであると、申し上げたいと思います。振動論によっても、建物の持つ固有モード毎に分析を行い、その解をたし合わせることにより、比較的簡便に用いることができます。従って、震度法のみならず建物の評価のために多様な解法が許容されることを望んでやみません。」
佐野が応えて、
「真島先生はただいま柔を評価するための簡便な方法として、振動論があると申されましたが、その真島先生が推奨される方法は、難解であり、正直申し上げますと、私もよく理解できないのであります。いかに優れた方法であるとしても、難解すぎて技術者の理解が得られないのでは、意味がないと言わざるを得ません。この度の震災により、首都圏は大きな被害を受けております。その回復は緊急の課題であり、そのためには、ある程度経済性も考慮した現実的な対応策を考える必要があります。先生の主張される振動論のような難解な手法では、問題の解決は困難と思われます。理想論では問題の解決にはなりません。
また、先生のお話をうかがっておりますと、柔の代表として、米国の200mを超えるような建物を想定されているように聞こえるわけでありますが、もしそうだと致しましたら、ほとんど正気の沙汰とも思われません。経済力を誇る米国に対し、我が国は先般の震災により疲弊の極に達しております。もっと現実的な復興策を迅速に推進する必要があるのでありまして、机上の空論にお付き合いする暇はございません。どうも先生は、理想論に目が奪われてしまって、現実を見ていらっしゃらないのではないでしょうか。
あえて失礼も省みず申し上げますれば、『清流に百年棲んで理想の実現を待つ余裕などは、われわれには無い』のであります。今望まれるのは、首都復興のための現実的な解決策であることを、忘れないで頂きたいと思います。」
真島は、議論が進むにつれ、無力感を感じていた。真島が主張したのは、多様性であり、建物を全て柔にしろというようなことでは無かった。もちろん首都復興が急務であることはわかる。しかし、だからと言って、法により未来永劫建物の形態に大きな制約を設けてよいものか。真島の主張はことごとく理想論として、一蹴された。しばらく、この国の建築は暗黒の時代へと向かうのであろうと真島は思った。
(稲田 達夫)