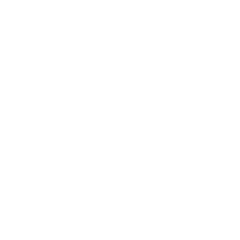News
2013/1~2014/12
2014年11月12日(水)日刊木材新聞一面より
◆CLT普及へロードマップ作成
林野庁が国交省と共同で 10年後50万m3の生産目標示す
林野庁は11日、国土交通省と共同で作成した「CLTの普及に向けたロードマップ」を公表した。2年後の2016年度までにオープン化に必要な基準強度、一般的な設計法の告示の制定を目指し、大臣認定で建築事例を積み重ねながら年間5万m3まで供給できる生産体制を構築する。燃えしろ設計の告示制定や床や壁などへの部分的な利用技術の開発も並行して進め、10年後の24年度には中層建築物(3~4階建て)の6%、年間50万m3規模の供給体制の整備を目指す。
現在、CLTを構造に使用しようとすれば、時刻歴応答解析などの特殊な構造計算で安全性を確かめ、国土交通大臣の認定を個別に取得する必要がある。また、規模などに応じた耐火措置が必要で、意匠面でCLTの特徴を生かせない現実がある。
基準強度(16年度)、設計法(同)、燃えしろ設計(15年度)の告示ができれば、大臣認定を必要とせず許容応力度計算などの比較的容易な計算で設計でき、3階建て以下の準耐火構造ならCLTを「現し」で利用できるようになる。
16年度までに告示制定を目指すのは1時間耐火構造で、4階建てまでの中層建築が対象になる。林野庁によると、実験などから耐震性能では7階建てまで可能と見ており、その後は2時間耐火の仕様の検討も視野に入るという。
また、超高層建築など非木造建築の床や壁、耐震補強にもCLTを利用できるようにするため、接合方法の開発も進める。これら部分利用は「技術開発ができ次第」と実用化の時期を明示していないが、構造の仕様と同様に16年度までには実用化させる意向だ。
告示制定までに構築する年間5万m3の生産体制は、CLT建築の第1号である高知おおおとよ製材の社員寮420棟分に相当する。現在、JAS認定工場は銘建工業、協同組合レングス、山佐木材の3工場で生産能力は年間1万m3だが、単一工場で年間4万~5万m3の工場を各地に整備し、10年間で50万m3まで引き上げる。生産性の向上により、現状で15万円/m3程度の製品単価を7万~8万円/m3まで低減させることを目指す。
CLTの実証建築は、今年度分として北海道北見市のセミナーハウス2階建て1棟、福島県湯川村の共同住宅2階建て2棟、岡山県真庭市の共同空宅3階建て3棟、群馬県館林市の事務所の居室(部分利用)、神奈川県藤沢市の診療所併用住宅(部分利用)の合計8棟が予定されている。
CLTの普及は今年6月に閣議決定された政府の成長戦略「日本再興戦略」「農林水産業・地域の活力創造プラン」に盛り込まれ、林業の成長産業化の切り札として期待されている。ロードマップは業界の取り組みを広く促すことを目的に作成された。
2014年10月30日(木)日刊木材新聞より
◆30階建てビルの試設計準備
杉CLTを床に使用 超高層ビルに木材を使用する研究会
超高層ビルに木材を使用する研究会(会長=稲田達夫福岡大学工学部教授)は18日、福岡市で第2回総会及び講演会・シンポジウムを開いた。
同研究会は諮問組織として林野庁委託事業「CLT等新製品・新技術利用促進事業のうちCLT実用化促進(接合部データの収集・分析)」(事業責任者・山佐木材)の各種研究に取り組んでおり、今回はその途中経過も報告された。また、稲田会長は杉CLTを床板に利用する場合の構造、耐火、施工性などの実験・データ収集、検証に加え、「イメージを持ってもらうために、30階建て程度の超高層オフィスビルで木床、木小梁を用いた試設計を一つ行い、資料をまとめたい」と話した。
基調講演は、神田順建築基本法制定準備会会長・日本大学特任教授・東京大学名誉教授が「建築における木材活用の意義」について話した。
神田氏は、「建築基準法に代わる”建築基本法”制定を目指す準備会を2003年に発足。現状の、法律をクリアすれば安全、責任を取る必要がないという考え方から、今後は自分、地域が自ら考え、文化、歴史と技能の融合による建築の時代に進んでいく」と指摘。「木造建築でも伝統工法住宅や高層ビルへの木材利用など、いろいろな使い方ができるようになることが重要で、地方産業の中心になる林業を守るにも、戸建て住宅に依存しない、幅広い継続的な需要が創出されることの方が重要だ」と話した。
シンポジウムは、コーディネーターに島田泰助全国木材組合連合会副会長、パネリストは稲田氏、神田氏、塩﨑征男山佐木材常務、塩屋晋一鹿児島大学教授、大熊幹章東京大学名誉教授が参加した。
杉CLTや杉・鉄筋を組み合わせたSAMURAI集成材の紹介、採用事例に加え、大熊氏は東京虎ノ門地区再開発事業で農林水産系事務所ビルの建て替えがあり、木床のCLT利用を含めて木材活用が検討されている状況を報告し協力を求めた。
島田氏は1950年代に国が非木造の街づくりの方向性を打ち出した状況から、現在は公共建築物等木材利用促進法をはじめ全く逆の方向に舵を切ったことを指摘。建築関係者に最優先で木材利用を検討するように考え方を変えてもらうための活動を業界全体で進めていくことが重要と指摘した。
2014年9月26日(金)
◆平成26年度予算による林野庁委託事業採択
平成26年度予算「CLT等新たな製品・技術の開発促進事業」のうち「中高層建築物等に係る技術開発等の促進(耐火部材開発)」について当社が採択されました
現在進めている平成25年度補正予算「CLT実用化促進(接合部データ等の収集・分析)」に引き続いての採択です。超高層オフィス建物の床のCLT化を実用化するために2時間耐火の性能を有する床構造をいかにして実現するか実験により検討します。
2014年9月6日(土)日刊木材新聞より
◆CLT床の高い施工性を確認
鉄骨フレームの施工実験を公開 山佐木材
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は8月27日、同社下住工場内で、杉CLTを用いた木床の施工性確認実験見学会を開いた。非木造建築の床にCLTを使用することを想定し、10.8m×7.2m(3.6mモジュールを想定)の柱・梁鉄骨造フレームの実大モックアップを作成。1.8m×3.6m×7層タイプの杉CLT床12枚を縦横に施工し、実際の設置・調整時間、接合部分の詳細など施工性の良否を確認する実験を公開した。
同社は、「超高層ビルに木材を使用する研究会」(会長=稲田達夫福岡大学工学部教授)と連携し、林野庁委託事業の「CLT等新製品・新技術利用促進事業のうちCLT実用化促進(接合部のデータ収集・分析)」を進めている。稲田教授は今回の実験概要説明で、高層ビルなどのコンクリート床を木床に置き換えていくにはコストが課題になるが、CLT生産体制の確立とともに、工期短縮、建物重量軽減効果、これに加えてCO2排出抑制や炭素固定、森林資源活用などの貢献度に見合ったインセンティブがあれば対抗できる可能性があると指摘。そこで最も重要な研究課題になるのが工期短縮、施工性向上だと話した。
今回の施工実験に用いられた柱・梁鉄骨造フレームは、鉄骨の組み方、溶接の仕方、スタッドの数などで様々な仕様を用意。杉CLT床を設置する過程や前後で、鉄骨・木床の精度、床の設置時間、床継ぎ目の不陸、同隙間、床の傾き具合、梁継ぎ手の不陸、柱・梁接合部の隙間、また降雨とCLT含水率などを詳細を調査する。
公開実験では、まずクレーンで杉CLT床を1枚ずつ吊り上げ、フレームに設置していく作業が行われた。鉄骨、木床の精度が高ければ、この作業は短時間で終えることができた。設置時間はスタッドの数などにも左右されるが、1枚当たり通常なら設置と調整を合わせて5~6分(速報値)だった。一方、クロスビス打設時間は1m当たりおおむね6~8分(同)。通常の高層ビルなどでコンクリート床を施工する場合は型枠施工の後、例えば100m以上の高さでもコンクリートをポンプアップして使用する。木床の場合は乾式工法であり、施工性の高さで優位性があるのは明らかになった。
今後は杉CLTの防耐火性能の確認(2時間耐火の取得)などにも取り組んでいく。
2014年9月3日(水)日刊木材新聞より
◆杉CLT用幅はぎライン棟建設
山佐木材下住工場
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は、10月をめどに杉CLT量産ラインを稼働させる計画だが、現在同社下住工場内に幅はぎライン棟の建設が進んでいる。同社は6月30日付で杉CLTのJAS認定を取得しているが、本命の全層幅はぎ評価プライのJAS認定は同ラインと同時並行で進め、秋から生産を開始する予定だ。
鉄骨挿入の高性能杉集成材「SAMURAI集成材」による18mスパンの大梁を採用した試作棟も完成し、今後は製品倉庫兼展示・検証施設として使用される。SAMURAI集成材は、一般の集成材に対して曲げ剛性が6倍になり、梁せいを55%小さくできる。18mの屋根梁でも、中央のたわみはクリープ変形後でも14mmしか生じない設計で、RC、S造と同等以上の構造性能を発揮する。
また、杉JAS集成材による床パネル、杉CLTによる試作棟や同製品を木床に用いるための柱梁鉄骨造フレームの実大モックアップ、杉2×4材の生産に向けた各種試験など、同社では様々な取り組みが進められている。
2014年7月19日(土)日刊木材新聞より
◆鉄筋挿入の高性能杉集成材
RC造と同等以上の構造性能 塩屋晋一鹿児島大学教授らが開発
杉構造用集成材の材長(繊維)方向に少量の鉄筋を挿入することでRC部材より高剛性・高耐力の構造性能を発揮する「SAMURAI集成材」、また同集成材を用いた「ウッドストロング工法」の実用化に向けた取り組みが進んでいる。鹿児島大学大学院理工学研究科建築学専攻の塩屋晋一教授が開発してきたもので、7月中にも山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)下住工場内に試作棟が完成する予定だ。今回はデモンストレーションの意味から18mスパンの大梁を採用した。
SAMURAI集成材は、45mm厚の杉ラミナにリサイクルの安価な鉄筋(D22~25)を挿入・接着(エポキシ樹脂)し、これを集成材の上下部分に配置して、後は通常の積層工程で製造する。
ウッドストロング工法の柱と梁、柱脚部の接合方法は従来の鉄筋接合によるラーメン構法と変わらない。異なる点は、▽柱と梁にSAMURAI集成材を用いる▽曲げ補強鉄筋と接合鉄筋は木部を介さず、直接応力伝達ができる継手を開発。具体的には接合部に航空旅客機で使われるJIS規格の炭素繊維とエポキシ樹脂接着剤による炭素繊維スリーブを用いる。スリーブ継ぎ手で接合された鉄筋は継ぎ手区間から抜け出すことがなく、鉄筋の母材が破断する性能を有する▽柱は二方向ラーメンの応力に有効に抵抗させるため、十字型、L型、T型を用いるなどだ。
構造性能を同工法とRC造で比較した場合、これまでの研究成果からはクリープ変形(たわみ)がRCの約半分に抑制される、部材の曲げ剛性は曲げひび割れを考慮するとRC部材と同等以上、曲げ強度も2倍以上になる(重量に対する曲げ強度・剛性で見ると優位性がさらに高まる)といったことが分かっている。Rウッド、米松平角などの横架材を用いたものはもちろん、RC造とも同等以上の構造性能を発揮する新たな木質ラーメン構造を実現できる可能性が高い。
さきごろ九州集成材組合(樋口吉徳理事長)が主催した見学会も行われ、50人以上が参加した。山佐木材では同建築物を製品・資材置き場として活用するとともに、同集成材・工法を普及するための展示施設として対応する考えだ。佐々木社長は「木造で直線的に18mのスパンを飛ばすのは良い選択とはいえないが、今回は木材、杉でもこれくらいできるということを知ってもらうために行った」と話していた。
2014年7月8日(火)日刊木材新聞より
◆杉CLTのJAS取得
生産能力は年4,000m3
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は6月30日付でCLT(直交集成板)のJAS認定を取得した。銘建工業(岡山県真庭市)に次いで、全国で2例目になる。樹種は杉。現状の生産可能サイズは最大で厚さ450×幅2000×長さ4000mm、生産能力は年間4000m3(1シフト)になる。
認定番号はJPIC-CL2。構成の種類が同一等級、異等級。ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆。構成の区分は3層3プライ、5層5プライ、7層7プライ、9層9プライ、5層7プライ、強度区分がMx60異等級構成(外層にM60B、内層にM30Bを使用したもの)、S60同一等級構成(全層にM60B)、S30同一等級構成(全層にM30B)。全種類B種構成での取得(曲げヤング係数の上限値を定めたラミナのみ使用)だ。使用環境はA、B、C(レゾシノール・フェノール樹脂。水ビはCのみ)。
今秋に新工場
今回は幅はぎ未評価プライでの取得だが、9月をめどに幅はぎラインを含めた杉CLT生産用設備を下住工場内に集約し、新工場を立ち上げる計画。10月ごろには全層幅はぎ評価プライ有りのJAS認定も取得して、生産できるよう取り組む計画だ。
同社は早くから構造用集成材面材(床、壁、天井)の提案、製造に力を入れてきた経緯があり、日本CLT協会の設立メンバーでもある。13年度は、同協会の林野庁助成事業で下住工場内に杉CLT2階建て実大試験棟を設置した。CLT複合床の床衝撃音遮断性能実験、また経年変化の確認などを行っている。
一方、CLTに先駆け、13年春には同一等級JAS集成材による杉床パネルが種子島の大型木造病院で採用され、高い評価を受けた。
これを受け、今年度は鹿児島県内の公立中高一貫校・寄宿舎でも採用されるなど、木材、また国産材の新たな需要分野として構造用面材の採用実績を広げている。
2014年7月5日(土)南日本新聞より
◆RCしのぐ集成材開発
県産材需要拡大に期待
鹿児島大学大学院の建築構造研究室(塩屋晋一教授)が、木材に鉄筋を埋め込んで剛性(硬さ)を飛躍的に向上させた鹿児島県産のスギの集成材を開発、山佐木材(肝付町)と共同で実用化に向けた実験棟を建設している。4日は現地で見学会があり、参加者から「県産材需要の拡大につながる」と期待する声があがった。
塩屋教授によると、国産スギを使った集成材の剛性はベイスギなどの外材製の半分程度しかなく、梁などの構造材に使うと大きくたわむ。このため、特に大規模木造建築で国産材の普及が進まない要員の一つとなっていた。
「SAMURAI(サムライ)集成材」と名付けた新集成材は上下に鉄筋が埋め込まれており、従来品の6倍の剛性を実現した。同じ断面積の鉄筋コンクリート(RC)と比べた場合でも、たわみを半減させる効果があるという。
実験棟(幅18m、奥行き20m)の建設は5月中旬から山佐木材敷地内で始まり、7月中の完成を見込む。4日の見学会には、行政や建築関係者ら約50人が参加し、塩屋教授や山佐木材担当者から説明を受けた。
「剛性工場でよりコンパクトな部材が使えるようになり、建築コストを20~25%削減できる。できるだけ早く実用化につなげたい」と塩屋教授。山佐木材の佐々木幸久社長も「RCをしのぐ性能を持つ建材で、木造の中高層建築も可能になる」と期待している。

2014年6月30日(月)
◆CLT(直交集成板)のJAS認定取得
当社が成長戦略の一環として取り組んでおりました、CLT(直交集成板)のJAS認定を6月30日付で取得しました。岡山の銘建工業様に続き、国内で二番目の認定工場となります。詳細は添付ファイルをご参照ください。
2014年5月4日(日)南日本新聞より
◆「木造ビル挑戦始動」 産官学連携、実用試験へ
新しいタイプの建材「直交集成板(CLT)」を使い、木造の中高層ビルを建てようという試みが、本格的に動き出している。昨秋、山佐木材(肝付町)など主に九州の産官学が連携した研究会が発足。2014年度には林野庁の事業を活用して実用化試験に取り組む予定だ。「新たな国産材需要を掘り起こしたい」と願う関係者の期待は大きい。
「海外ではCLTを使ったビルやマンションがどんどん建てられている。日本でも普及させない手はない」
10年以上前からCLTに着目していたという山佐木材の佐々木幸久(67)が語る。「やっと機運が盛り上がってきた。うちも9月ごろには本格生産に取りかかるつもりだ」
CLTは1990年代半ばに、欧州で開発された集成材製法。通常の集成材はひき板の繊維が並行するように重ねて作るが、CLTは直交させて張り合わせる方法で、耐久性を高め、高層建築に必要な強度を得ることができるようになった。
利点は強度だけではない。佐々木社長は「コンクリートパネルの5分の1の重さですむので、建物の耐震性も高まる」と強調。製材工場で加工して出荷するため、工期も短縮できるといい、実際に欧州では9階建てマンションを9週間で完成させた例もあるという。
CLTは既に欧州、北米では年間50万立方メートルの市場を形成、木造建築の新たな可能性を切り開いてきた。一方、日本での普及には、いくつかの課題がある。
その一つが建築基準法による規制だ。国内では、原則としてJASかJISの規格認定を受けた部材でなければ建物の主要構造に使えない。国土交通大臣の認定を受ければ非規格品も使えるが、「一般に広く普及させるには、規格化が不可欠」(佐々木社長)だった。
そこで山佐木材は2012年1月、同様にCLT製造技術を持つ銘建工業(岡山県)、レングス(鳥取県)と共同で日本CLT協会を立ち上げ、認定に向けた試験を実施。14年1月、JAS規格施行にこぎつけた。
こうした動きと並行し、九州では13年10月、産官学連携による「超高層ビルに木材を使用する研究会」が発足した。事務局は山佐木材が務め、鹿児島県工業技術センター職員も名を連ねる。まずは床材としての活用を目指し、試験・研究を進める方針だという。
ただJAS規格化で普及を阻む壁がなくなったわけではない。CLTは今までにない建材だけに中高層建築に求められる構造計算用の「基準強度」のデータがない。現状でCLT製の建物を造るには、1千万円ほどのコストをかけ特殊な計算方法を用いる必要がある。
林野庁は13年度から基準強度を定めるためのデータ収集に着手、国交省と連携し早期の基準策定を目指す考えだ。山佐木材も14年度、林野庁に提案していた実用化試験が採択され、CLTと鉄骨などを接合する際の強度計算に取り組む。同社は研究会メンバーとも協力しながら作業にあたるという。
課題はまだある。建築規制を乗り越えても一般的な建材の3倍という製造コストを削らなければ、欧州製CLTとの競争に勝てない。新工法の周知活動も欠かせないだろう。
それでも「CLTが木材需要拡大の可能性を秘めていることは確か」(県かごしま材振興課)だ。堂込清文課長は「『木造ビル』が建つまでには、まだ時間がかかるだろうが、国や関係団体などと情報交換しながら普及への努力を続けていきたい」と話している。

2014年4月22日(火)日刊木材新聞より
◆全寮制中学・高校の寄宿舎で床用杉パネル採用
CLT含め山佐木材が生産体制整備
鹿児島県に来年開校する中・高一貫校の学生用木造寄宿舎で、杉集成材厚板床パネルが採用されている。同県内では昨年建設された木造大型病院でも同材が採用されている。木材、また国産材の新たな需要分野としてCLTを含めた構造用面材の今後が注目を集めるなか、実際の需要が全国に先駆けて動き出している。製造元は山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)。
木造寄宿舎が建築されているのは、来年4月に開校予定の鹿児島県立楠隼(なんしゅん)中学校・高等学校。全国初の公立全寮制男子校で、難関大学を目指した6年間のカリキュラム、また地元肝付町に内之浦宇宙観測所があることから、JAXAと連携した宇宙、科学に関する教育活動も予定され、話題になっている。
敷地、施設は高校再編で閉校する現在の県立高山高校のものを活用するが、全寮制の生徒用寄宿舎が木造(最終的に6棟)で新築される。既に1期生120人の受け入れに向けて寄宿舎2棟などの建築が始まった。
柱・梁を含めた構造用集成材全般の供給は山佐木材が担う。このうち杉集成材厚板床パネル(同一等級JAS)は寄宿舎1棟当たり100立方メートルが使用される予定だ。同社は13年春に鹿児島県種子島で開院した医療法人純青会せいざん病院(延床面積5300平方メートル強の木造2階建て)向けに、今回と同様の杉床パネル260立方メートル強を納材した実績がある。これが利用者、設計関係者などから高い評価を得ており、今回の提案、採用にもつながった。日本集成材工業協同組合が国産材集成材厚板床パネルで1時間準耐火の国土交通大臣認定を取得していたことも後押しした。
山佐木材は、新たな木材需要分野に対応するため、今年度からCLT生産用プレス、ラミナ生産ラインなどの設備投資を開始する。需要動向に合わせて徐々に拡大、また工場集約化を進めていく計画。同時に国産材集成材厚板床パネルの将来性も高く評価しており、今後も製造、提案に力を入れていく考えだ。
2014年4月22日(火)日刊木材新聞より
◆普及・拡大に積極活動
国産材の新需要分野開拓も 山佐木材
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)は、従来にも増して様々な木造物件用の国産材構造用集成材供給メーカーとしての存在感を高めている。地域材を使った木造建築が各地で実現、検討されるなか、杉大断面構造用集成材のパイオニアメーカーとして地域材(ラミナ)を活用した構造用集成材製造に様々なノウハウを持つ同社に供給依頼が寄せられている。
校舎、体育館、公民館などはもちろん、昨今では木造庁舎、図書館などでも木造建築の事例が出てきている。昨今では熊本県上天草市の松島庁舎、鹿児島県霧島市の横川総合支所庁舎、また熊本市の城南図書館・児童館などに製品を供給した。
国産材の新需要分野開拓にも積極的に動いている。特に近年は構造用面材に力を入れており、昨年は鹿児島県種子島の大型病院で杉床パネル(マッシブホルツ)の実用化にも取り組んだ。CLTでは日本CLT協会の設立メンバーとなり、九州では「超高層ビルに木材を使用する研究会」(会長=稲田達夫福岡大学工学部教授)の立ち上げにも尽力した。同研究会はオフィス用床でCLTが活用できないか、建築はもちろん様々な専門分野の関係者と検討を進めている。2013年林野庁補正予算「CLT等新製品・新技術促進事業」のうち「CLT実用化促進(接合部データ等の収集・分析)」でも採択を受け、実験により課題を検証していく予定だ。鹿児島大学で開発された鉄筋補強集成材(SAMURAI)の実用化にも取り組んでいく。
2014年3月28日(金)
◆SAMURAIの試作建設大臣認定取得
鉄筋補強集成材(SAMURAI)による加工場建築について、国土交通大臣認定を取得しました
弊社敷地内にスパン約18 m、奥行約20 m、1階建ての加工場を試作建設するための大臣認定がおりました。18 mスパン方向は鉄筋で補強(鉄筋を内蔵)したスギ集成材【断面180 × 600 mm】を水平に架けたもので、梁間に柱はありません。柱にも配筋したものを使用します。
2014年3月27日(木)
◆平成25年度林野庁補正予算による委託事業採択
平成25年度林野庁補正予算「CLT等新製品・新技術促進事業」のうち「CLT実用化促進(接合部データ等の収集・分析)」について当社が採択されました
「超高層ビルに木材を使用する研究会」で提案してきた”超高層オフィス建物の床のCLT化”を実用化するための課題を実験により検証していく予定です。
主要な実験は公開することも検討しております。詳細は追ってご案内いたします。
2014年3月11日(火)日刊木材新聞より
建築基準整備に向けて 日本CLT協会が活動本格化
日本CLT協会(中島浩一郎会長)は、CLT建築物の普及・拡大に向けて14年度第1次募集を行い、正会員78社、特別賛助会員(行政)5者の83者が集まった。4月には一般社団法人化して河合誠三井ホーム顧問(元常務)を専務理事に迎え事務局体制を整える。各種委員会を立ち上げ、CLTの基準整備に向け支援を行っていく。防耐火や遮音性能などについては独自の認定取得も視野に活動していく方針を示した。
2014年3月2日(土)南日本新聞より
楠隼中・高校の寮建設で工事安全祈願祭 肝付町
2015年4月に開校する楠隼(なんしゅん)中・高校(肝付町)の敷地内に置く寮建設工事の安全祈願祭が1日、開かれた。鹿児島県教育委員会や施工関係者ら約60人が参列、工事の無事を祈った。
同校は高校再編に伴い15年度末で閉校する高山高校の施設を活用して開設。公立では全国初の全寮制男子校となる。16年度までに寮計6棟を順次新設し、総工費48億円。中高の1期生計120人の受け入れに向けては、14年10月末までに寮2棟や食堂棟、浴室棟を整備する。
2014年2月19日(水)日刊木材新聞より
鹿児島県霧島市に『2×4用杉スタッド工場新設』
さつまファインウッド 地域でサプライチェーン構築へ
さつまファインウッド(鹿児島県曽於市、林雅文社長)は、鹿児島県霧島市の国分上野原テクノパーク内に2×4用杉スタッド材の加工工場を新設し、2015年4月から操業を開始する。鹿児島県内の原木、製材関係者と連携した国産材のサプライチェーンを構築し、大東建託向けの長期契約販売を中核とした国産材の安定供給、新需要開拓に挑戦する。製品生産量はフル操業時で年間4万4000立方メートル(原木換算で約10万立方メートル)を見込み、うち8割が2×4用杉スタッドになる計画だ。
さつまファインウッドは13年11月に設立され、資本金は4000万円。出資比率は、伊万里木材市場(佐賀県伊万里市、林雅文社長)3300万円、山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)400万円、鹿児島県木材協同組合連合会300万円になる。操業開始にあわせて本社も霧島市に移す予定だ。事業所名は「さつまファインウッド かごしま材JAS製品流通加工センター(仮称)」。用地面積4万4000平方メートル、建物面積9075平方メートルで、今年4月から着工し、来年4月の操業開始を予定する。投資予定額は22億円(用地取得費含む)、年商は15億円(初年度は12億円)を見込んでいる。従業員数は20人で、うち19人を地元から雇用する。
2014年2月18日(火)南日本新聞より
霧島に国産材加工工場
さつまファインウッド 市と立地協定
「さつまファインウッド」(曽於市、林雅文社長)は17日、霧島市の国分上野原テクノパークに建設する国産材をツーバイフォー(2×4、壁組み工法)用に加工する新工場の立地協定を結んだ。4月着工、来年4月操業予定。立地すれば、上野原テクノパークの分譲率は89.8%となる。
さつまファインウッドは、木材卸売・加工販売の伊万里木材市場(佐賀県伊万里市)のほか、山佐木材(肝付町)、鹿児島県木材協同組合連合会が出資する新会社。製造する木材はマンション運営大手の大東建託に供給する。
建設する新工場「さつまファインウッドかごしま材JAS製品流通加工センター(仮称)」は、敷地面積4万4338平方メートル、建物面積は9075平方メートル。19人を新規雇用する予定。投資予定額は22億円、初年度は12億円の売り上げを目指す。林社長は「地域の林業や木材産業の活性化に役立ちたい」と話した。
伊万里木材市場は南九州の資源量に注目し、2011年、曽於市に営業所を開設。国産材の需要先を確保するためには、品質を保証する日本農林規格(JAS)化が必要として、新工場を計画。
南九州の原木を集めやすい霧島市に立地を決めた。大東建託も、為替変動に左右されず安定的に調達できる、同工法用の国産材を求めていた。
2014年1月16日(水)日刊木材新聞より
『木質混構造で6階建』
県産杉CLTを活用 高知県自治会館新庁舎
高知県総合事務組合(高知市)は、事務所を置く自治会館新庁舎の建築に伴う基本設計業務で、昨年6月に公募型プロポーザルを実施し、審査の結果、細木建築研究所(高知市、細木茂代表)が提案した木造・SRC造の混構造による6階建てでの建築を採択した。
建物は6階建ての下3層がSRC、上部3層が木造というハイブリッド構造になる。1フロア600平方メートル、延べ面積は3600平方メートル、1階と2階の間に中間免深層を設けて木造部分の耐震性を担保する。
木造部分は基本的に県産材の集成材による木造軸組構造で一部の耐力壁にもCLTを用いる。耐火建築物のため構造材には被覆を施すが、被覆の必要がない筋違とカーテンウォールとを組み合わせることで木質感を高める。また内装間仕切りにCLTを用い、内・外装にも積極的に県産材を使う計画だ。
2013年12月20日(金)CLTのJAS規格(日本農林規格)が制定されました
CLTは、ひき板を幅方向に並べたものを繊維方向が直交するように積層接着した製品で、欧米を中心に、中・大規模のマンションや商業施設の壁や床に用いられるなど急速に普及が進んでいるものです。
平成26年1月にJAS規格が施行された後、登録認定機関による製造業者等の認定を経て、JASマークの付されたCLTの流通が始まります。
2013年12月6日(金)日刊木材新聞より
『耐火建築の制限緩和を次期国会で』
基準改正見越し木造3階建て校舎の取組も
自由民主党循環型社会形成のための木材利用推進議員連盟は4日、耐火建築物の規模制限や学校などの階数制限の緩和についての建築法改正、国交省・文科省・林野庁は基準改正を見越し木造3階建て学校建設をはじめとした木材利用の取り組みを始めることなどの内容を盛り込んだ「大規模木造建築物への木材利用の促進に関する決議」を採択した。また参議院では防災・減災等に資する国土強靭化基本法が採択され、土木工事における木材利用を促進し、そのための技術開発・試験研究を進めるという付帯決議も行われた。
2013年12月3日(火)日刊木材新聞より
『CLTの建て方を公開 高知おおとよ製材社員寮 国内初の物件』
地組み後2日で上棟
構造躯体にCLT(直交集成板)を使った社員寮の建築が進む高知県内の現場で11月30日、構造見学会が開かれた。
CLTの製造プラントを保有する銘建工業(岡山県真庭市、中島浩一郎社長)が出資する高知おおとよ製材(高知県長岡郡、同)の社員寮として建築するもの。
今回の建て方工事はCLTを構造躯体に使った国内初の事例として注目されている。当日は全国から国や県の行政関係者や研究機関、ゼネコン、設計士、ハウスメーカー、資材流通業約300人が参加した。
2013年8月2日(金)日刊木材新聞に弊社ホームページが紹介されました
山佐木材(鹿児島県肝属郡、佐々木幸久社長)が、約10年ぶりにホームページをリニューアルした。1990年に全国で初めて杉構造用集成材のJAS認定を取得して以来、木造で手掛けた公共及び民間施設は1000件近くになっており、施工実績や商品等が写真等で見やすくなった。
過去に季刊誌として発行してきた「ウッディストのたより」もアーカイブが作られた。同たよりの最新号(16号)は木造オフィスを中心に掲載するほか、国産集成材厚板パネル、CLT、ホウ酸表面処理(ボロンdeガード工法)による白アリ対策等を紹介している。10月からはメールマガジン配信も開始する予定だ。
一方、「超高層ビルに木材を使用する研究会」の会員も募集している。同会は、超高層ビルの設計業務に長年携わってきた稲田達夫福岡大学工学部教授の提唱によるもので、今年5月に福岡大学工学部で設立準備委員会を立ち上げた。10月をめどに福岡市で設立総会及び講演会を開催する計画だ。事務局を山佐木材が務める。
2013年6月26日(水)日刊木材新聞より
『1時間準耐火構造の大臣認定取得 国産集成材厚板パネルの木造床組構法で』
日本集成材工業協同組合(日集協)は、国産集成材厚板パネルを用いた木造床組構法で1時間準耐火の国土交通大臣認定を取得した。これにより、木造3階建て共同住宅などでの利用が可能となり、集成材の面材利用といった新たな用途開拓が期待でされている。
2013年4月6日(土)日刊木材新聞より
『1時間準耐火の大臣認定取得予定 集成材厚板床パネルで』
日本集成材工業協同組合(日集協)は近く、集成材厚板床パネルで1時間準耐火の大臣認定を取得する。1月に耐火性能評価試験を実施し、合格基準を満たしたため、(財)ベターリビングから3月12日付で評価書が交付された。試験体には杉が用いられたが、評価範囲は比重が杉以上のトド松やカラ松、アカ松で申請する。


〒893-1206
鹿児島県肝属郡肝付町前田2090
TEL:0994-31-4141
FAX:0994-31-4142